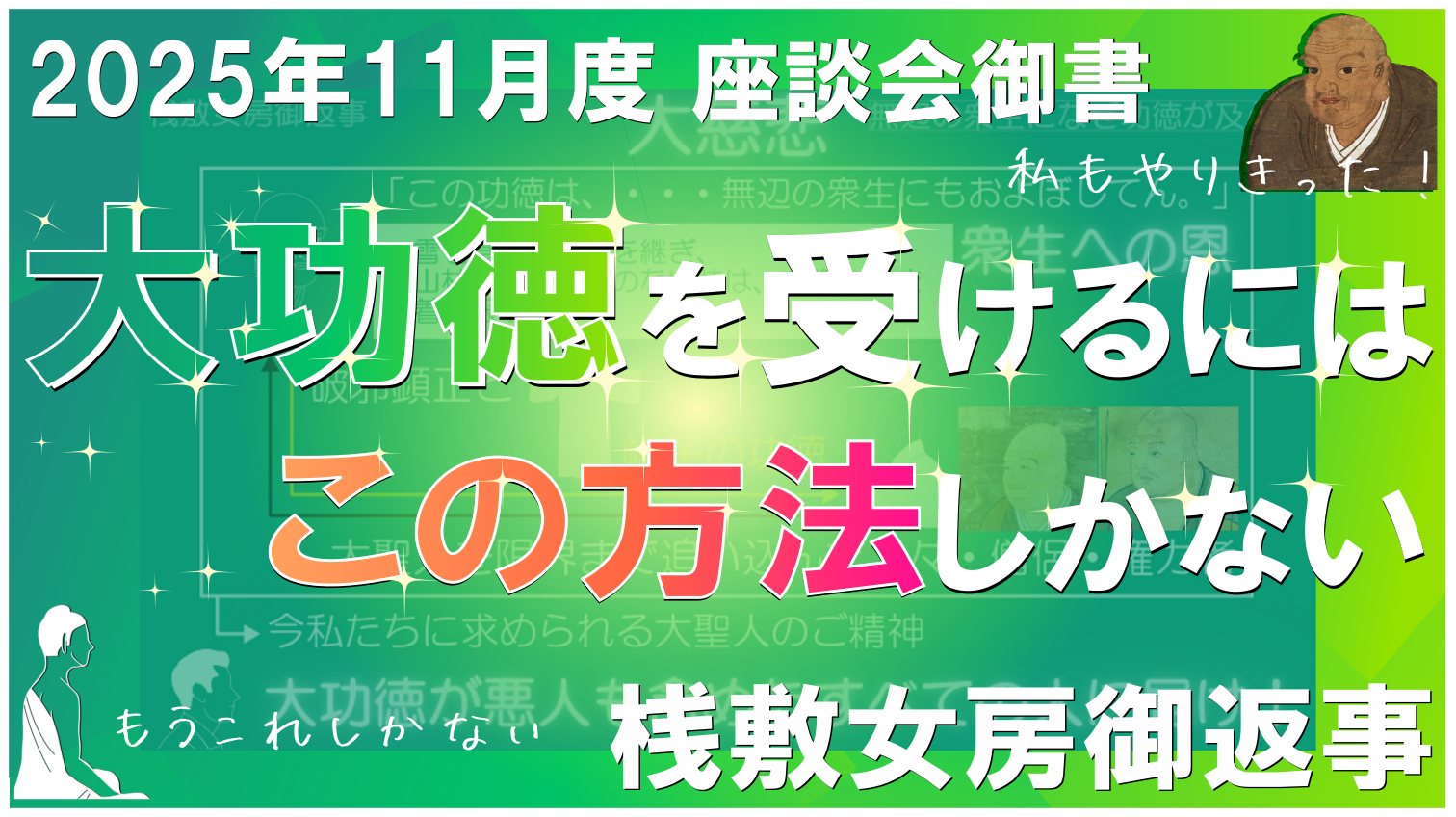
2025年11月座談会御書 桟敷女房御返事
みなさん、こんにちは
11月度の座談会拝読御書は、桟敷女房御返事(無量無辺の功徳の事)です。
動画はこちらにアップしております。
それでは今月も元気に学んで参りましょう!
拝読御文
たとえば、はるの野の千里ばかりに
くさのみちて候わんに、
すこしきの豆ばかりの火を
くさひとつにはなちたれば、
一時に無量無辺の火となる。
このかたびらも、またかくのごとし。
一つのかたびらなれども、
法華経の一切の文字の仏に
たてまつるべし。
この功徳は、父母・祖父母・
乃至無辺の衆生にもおよぼしてん。
全 1231ページ9~12行目
新 1704ページ11行目~1705ページ2行目
通解
たとえば、春の野が千里ほどにも広がって
草が生い茂っている所に、
豆粒ほどの小さな火を一つの草に放つと、
いっぺんに無量無辺の火となる。
(あなたが供養した)この帷子も
また同じことである。
一つの帷子ではあるが、法華経の一切の文字の
仏に供養したことになるのである。
この功徳は、父母、祖父母、さらに
限りなく多くの人々に及ぶに違いない。
背景と大意
本抄は建治元年1275年5月25日、日蓮大聖人が54歳の時に鎌倉の女性門下である桟敷の女房に送られたお手紙です。
本抄は、桟敷の女房から届けられたご供養、帷子に対しての感謝とその功徳について仰せになられたお手紙です。
本抄は、5月度の座談会御書で学んだ単衣抄の3か月前のお手紙であり、単衣抄の中で「3月4月は裸で過ごした」と仰せになられていることから、
佐渡流罪赦免後、鎌倉を経て身延に入られた大聖人がどれほど困窮した状態にあったかは想像を絶します。
8月にご執筆のお手紙単衣抄に「3月4月は裸で過ごした」と書かれていることから、本抄の桟敷の女房から送られた帷子が2か月ぶりに着た衣服だったのかもしれません。食べ物もなく山林に入って自ら食料を調達しなければならなかった状態であり、その中で送られた帷子に大聖人がどれほどお喜びになられたか、末法のご本仏が一人法のため、民衆のために身命を惜しまず戦い抜かれたことに改めて感涙を流さずにはいられません。
桟敷の女房についてその詳細は不明ですが、本抄で夫が法華経の行者であるとの言及があることから、夫婦で共に信心に励んだ門下と拝せられます。
本抄ではまず、女性、特に鎌倉時代における女性の特徴や役割について言及されるところから始まります。
女性は、水、矢、船の楫などの例を通して、共に人生を歩む夫がどのような人であるかによってその人生が左右されやすい面をご指摘になられます。
続いて、桟敷の女房については、法華経の行者である夫をもつことは仏もご存じのことであり、さらには、このように帷子の供養までしていることは、まことに尊いことであるとご賞賛になられます。
たとえ一枚の帷子であっても、それは聖人が身をはいだ皮に写経するのと同じ功徳があり、それは法華経の69,384文字の仏に供養したこと同じ
たとえれば、千里の草原に、小さな火をともせばたちまち無量無辺に広がるのと同じであると仰せになられます。
そしてその功徳は、供養した人のみならず、父母、祖父母、さらには多くの衆生にも
及ぶ絶大なものであり、夫に功徳が及ぶことは言うまでもないとご断言になり本抄を結ばれています。
拝読箇所の解説
たとえば、はるの野の千里ばかりに
くさのみちて候わんに、
すこしきの豆ばかりの火を
くさひとつにはなちたれば、
一時に無量無辺の火となる。
このかたびらも、またかくのごとし。
無量無辺とは計り知れないことの意味であり、草原が続く限り火が燃え広がるように、
その功徳は限りなく広がっていくと仰せです。
鎌倉時代の1里はだいたい500mぐらいであったと言われることから、千里とは500キロ程度をイメージされていると思われ、当時としてはどこまでも続くように感じられるほど遠くまでという意味で仰せになったと拝されます。
帷子とは、桟敷の女房から送られたご供養で、裏地のない単衣の着物のことです。
なぜ帷子一つでそのような功徳があるのかという点についてですが、これはただ単に法華経の絶大な功徳を比喩したものにとどまらず、
当時唯一法華経を広める存在であられた末法のご本仏である日蓮大聖人が実質的に衣食住が足りず困窮状態、粗末な住居、食事は山林に入って自給自足
衣服はなく、一般的に見れば人としての尊厳すら危ぶまれる生活にあってその一枚の帷子が、どれだけご本仏の命をつなぎ留め、実質的に今日の法華経流布への礎となったかこのことを考えれば、法華経一文字一文字の仏、69,384の仏に供養した功徳があるというのは、全く大げさな話ではないのです。
一つのかたびらなれども、
法華経の一切の文字の仏に
たてまつるべし。
この功徳は、父母・祖父母・
乃至無辺の衆生にもおよぼしてん。
たった一枚の帷子であっても、法華経の文字の数だけの仏に供養したことになり、そしてその功徳が、供養した本人のみならず父母、祖父母、さらには限りなくすべての衆生に及んでいくとご断言です。
深堀ポイント
これから御書を研鑽される方のために、深堀していきたいポイントを確認していきます。
今回の深堀ポイントは、なぜ功徳が桟敷の女房だけにとどまらず、無辺の衆生にも及ぶのかという点です。
法華経を供養することに絶大な功徳があるとは、これまでも様々な御文で大聖人が断言しておられることであり、唯一万人成仏をとく経典、あらゆる人を成仏せしめ、幸福に導ける法であることから、これまで御書をしっかりと研鑽されてきた方ならば、そのことについては疑問がないのではと思います。
しかし本抄においては、その供養をおくった人のみならず、親類、さらには、無辺の衆生にも及ぶと仰せになり、ここまでの功徳が語られたことはあまりありません。
自分やその家族までならばまだしも、無辺の衆生、つまり衆生が誰であるかを問わず、その功徳が及ぶとはどのようなことでしょうか。
当該の御文をその直後まで確認してみます。
この功徳は、あなたの父母、祖父母、更に多くの衆生にも及ぶことは当然です。
まして、あなたの最愛の夫に功徳が及ぶことはいうまでもないとよくよく確信していきなさい。
この功徳が及ぶ対象として、真っ先に父母、祖父母、そして最後に夫のことに言及されていることから、ここに列挙されている人々は、桟敷の女房が今ここで信心に励み、そして大聖人に供養を届けるに至ったことにかかわる人たちとい意味に拝することができます。そして、その文脈で見ていけば、ここで「限りになく多くの人々」に言及されていることは、それらの人々もまた、桟敷の女房という信仰者を生み出し支えている功徳があると拝することができるかと思います。
つまりこの御文において大聖人は、一切衆生を報恩の対象であると捉えているがゆえに、
桟敷の女房の功徳が、「限りなく多くの人々」に及ぶとご断言なのではないでしょうか。
大聖人は開目抄で次のように仰せです。
「仏弟子は必ず四恩をしって知恩・報恩をいたすべし」
開目抄
四恩とは、恩を報ずべき4つの対象のことで
- 一切衆生の恩
- 父母の恩
- 国王の恩
- 三宝の恩
その中に一切衆生の恩というものを挙げられています。
そして一切衆生に恩を報ずるべき理由は次のように述べられています。
「一切衆生がいなければ菩薩の四弘誓願の一つである衆生無辺誓願度の願いを発すことは難しい。
また正法誹謗の悪人がいなくて菩薩に留難を加えないならば、どうして功徳善根を増していくことができようか。」
四恩抄
ここでは一切衆生に恩を報ずるべき理由が2つ挙げられていて、1つ目は衆生無辺誓願度があるからです。
衆生無辺誓願度とは、衆生をかぎりなく苦悩から救っていこうとの誓願です。
2つ目は、正法誹謗の悪人がいなくては菩薩が功徳善根を増やしていくことができないからと言われています。
一切衆生への報恩の理由としては、特に2つ目に挙げられている理由が衝撃的と言えます。
誰かのおかげで今の自分があるという話はもちろんのこと、ここで言及されていることは、正法誹謗の悪人でさえも報恩の対象になりうるということです。
この「仏弟子は必ず四恩をしって知恩・報恩をいたすべし」の開目抄の御文は、
ご執筆が本抄の3年前、佐渡流罪中にご執筆されたことを考えれば、大難の中にあっても、大聖人の御心の中には、正法誹謗の人でさえも報恩の対象にすべきとの思いが明確におありになったことが分かります。むしろ正法誹謗の人だからこそ報恩の対象なのだとさえいえるかもしれません。
まさにご本仏のご内証です。
ここまでの意味を再度拝していくと、今月の座談会御書の最後の箇所の御文が甚深の意味をもって迫ってきます。
「この功徳は、父母・祖父母・乃至無辺の衆生にもおよぼしてん。」
まさに父母や祖父母のみならず、無辺の衆生、そしてたとえ法華経を誹謗した悪人にさえも、この帷子の功徳、69,384の仏に供養する功徳がとどいていくということになります。
背景と大意で学習したように、この時大聖人はご自身に及んだ最大の難である佐渡流罪の直後であり、しかも、赦免後も鎌倉、身延に入ってもなお続く困窮の中にありました。
自身を限界まで追い込んだ人々、僧侶、権力者からの仕打ちはいまだに続いていたと言えます。
住居を奪い、食べ物を奪い、服の最後の一枚までも奪われた。
しかしその中で大聖人が示されたのは、戦いの炎はまだ消えていないという闘志、これほどの仕打ちを犯した人々に対する破邪顕正の精神と共に、その人たちでさえも自分に供養された帷子の功徳によって暖かく包んでいくのだという、あまりにも深い大慈悲です。
どれだけ杖で打たれても、どれだけ罵声を浴びせられようとも、その方々への報恩の思いを忘れない、今私たちに求められているのは、この大聖人のご精神ではないでしょうか。
自身の広布前進への行動が、その功徳が、少しでもその人たちを包みこんでいくようにと祈っていこうではありませんか。
その境地に立ってこそ、我が弟子ここにありと大聖人がお喜び、ご賞賛されるに違いありません。
もっと教学にJOINして教学を楽しく深めよう!
サイトを見てみるもっと教学とは?
本サイトは創価学会での教学をより一層深めるためのサイトです。
人間革命や御書、その他教学に役立つ書籍のチェックリストや感想を投稿できます。
読了チェックシート
読了した本やチャプターを簡単に記録し、進捗を管理できます。
感想を投稿・シェア
読んだ御書や人間革命について感想を投稿できます。
題目カウント
毎日の唱題・勤行の記録ができます。ホーム画面で全国の合計題目数も見られます!
研鑽バッジ
研鑽の進捗や日々の研鑽状況に応じてバッジを付与します。
拍手機能
素晴らしいと思った活動に拍手をおくることができます。