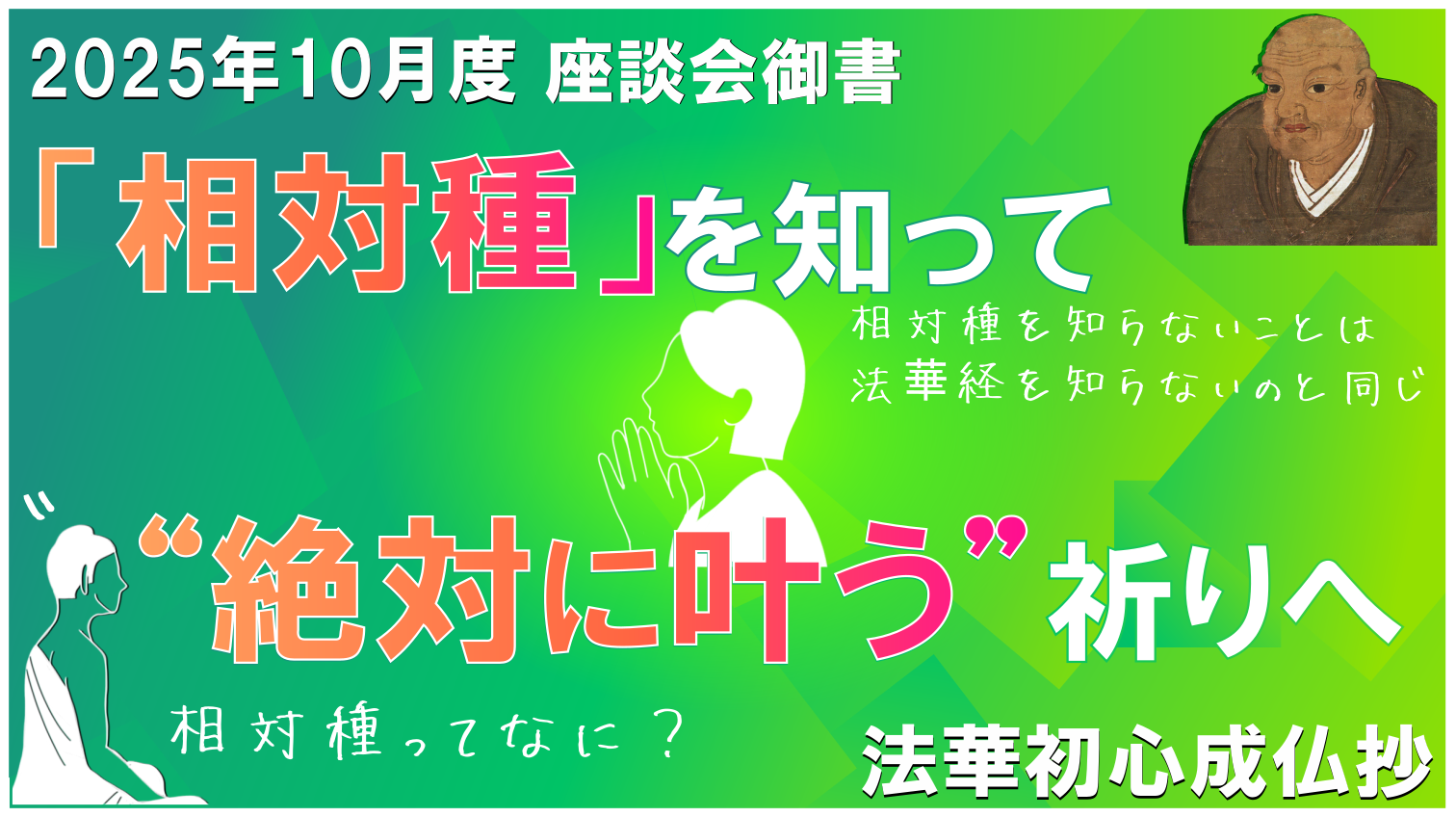
2025年10月座談会御書 法華初心成仏抄
10月度の座談会拝読御書は、法華初心成仏抄です。
それでは今月も元気に学んで参りましょう!
動画のほうはこちらです。
拝読御文
とてもかくても法華経を強いて
説き聞かすべし。
信ぜん人は仏になるべし。
謗ぜん者は毒鼓の縁となって
仏になるべきなり。
いかにとしても、仏の種は
法華経より外になきなり。
通解
とにもかくにも法華経を強いて
説き聞かせるべきである。
信じる人は仏になる。
謗る者は毒鼓の縁となって仏になるのである。
どちらにしても、仏になる種は
法華経より他にないのである。
全 552ページ 14~16行目
新 697ページ 14~16行目
背景と大意
本抄は建治3年1277年、日蓮大聖人が56歳の時にご執筆されたとされている書です。ただ御真筆がすでに現存せず、対合衆は不明であり、ご執筆の時期も様々な説があります。
本抄は全17章にわたる長編であり、すべてが問答形式で展開されています。その結論は、南無妙法蓮華経こそが末法に於いてただ唯一の成仏の法であるということです。
本抄ではまず法華経以前の諸経と法華経を比較して、法華経のみが仏が建立した宗であると仰せになられます。
法華経以前の諸経をよりどころとする宗派と、法華経をよりどころとする法華宗を比較して法華経をよりどころとする宗派のみが仏が建立した宗であると仰せになられます。法華経以外をよりどころとする宗派が我が経こそ勝れりとしているが、それらは皆後の人によって作られた邪義であり、法華経のみが仏説によって法華経に及ぶ経はないと説かれているとご断言になられます。
世間では法華経はその時代や人々の機根によって用いるべきか否かがあると言われているが、
そもそもすべての経は法華経によって成仏するための教えであって、その優劣は明らかであり
爾前経で得道するなどというのは、仏の本懐を否定する者であると断じられます。
特に末法に於いては、その功徳が保証された経は法華経のみであって、
諸経において末法に功徳があるというものは皆誤った解釈をしていると仰せになられます。
つづいて、
よき檀那が、よき師、よき法によって祈るとき国の大難も払うことができる、そしてそれは、たとえ無智のものであっても、強いて法華経を説き聞かせる、末法に於いては南無妙法蓮華経を聞かせることでしか成就する道はないと仰せです。
南無妙法蓮華経を信じれば成仏し、たとえ謗ることがあったとしても毒鼓の縁により、いずれにしても成仏するとご断言になられます。
法華経は悪人、女人、二乗を含めたすべての人の成仏を説く未曽有の法であり、その行者は、三類の強敵が出現し行く手を阻まれるが、これこそが
正法を行じるものの証であり、それは経文に照らしても、また過去の法華経の行者にも起こったことであって、そのことは疑いようがないと仰せになられます。
最後に、法華経自体に法華の名を受持する功徳がどれほどとも量りがたく、素晴らしい功徳であるかと記されている通りである、ゆえに私たちは、我が胸中の妙法蓮華経を本尊とあがめて、南無妙法蓮華経と唱えるのであり、それにより己心の仏性が呼ばれて仏となるのである
それこそが三世諸仏の出世の本懐であり、一切衆生が皆仏道を成ずる妙法なのであると仰せになられ本抄を結ばれています。
拝読箇所の解説
とてもかくても法華経を強いて
説き聞かすべし。
当時多くの人が法華経を用いず念仏などの誤った教えを信仰していたがゆえに、法華経を説いた結果、たとえ反発してその人が法華経を謗る罪を犯してしまうことになってしまったとしても、いずれにしろ地獄におちるという結果は変わらないため、法華経を強いて説き聞かすべきであると仰せの箇所です。
強いて聞かせるとは、強引に聞かせるという意味ではなく、あえてという意味で用いられています。
あえてというのは、特別な意図をもって、困難やリスクを承知のうえでなどの意味ですから
ここでは、たとえ相手が法華経を誹謗するとわかっていても、それでも説き聞かせるべきであるという意味です。
信ぜん人は仏になるべし。
謗ぜん者は毒鼓の縁となって
仏になるべきなり。
信じる人はもちろん仏に成り、法華経を聞いた結果、法華経誹謗をしたとしても、その人は毒鼓の縁で、やはり仏に成ると仰せになられます。
毒鼓の縁とは、涅槃経に説かれる法理の一つで毒を塗った太鼓の音を聞くと煩悩が死ぬという、逆縁の功徳を例えた言葉です。
法華経誹謗は五逆罪をも上回る罪であって、長く地獄に堕ちることにかわりはありませんが、法華経を誹謗したその逆縁によってやがては成仏する
つまり相手がどのような反応を示そうともやがては成仏していくことに代わりはない、だからこそすべての人にひとえに南無妙法蓮華経を説き聞かせて行くべきであると仰せなのです。
いかにとしても、仏の種は
法華経より外になきなり。
末法に於いては、すでに諸経が力を失っており、ただ唯一成仏の道は法華経つまり南無妙法蓮華経を唱えることによって開かれると仰せです。
いかにとしてもは、どちらにしてもの意味で、この一説に於いては、法華経を誹謗するにせよ信じるにせよということです、
つまり法華経を説き聞かせた結果がどうなったにせよ、成仏の道は法華経以外にないのだから、一見自分の機根にあっていそうな
法華経以外の経典を用いる意味は最初からないということになります。
深堀ポイント
今回の深堀ポイントは、
毒鼓の縁となって仏になるとはどういうことかという点です。
毒鼓の縁はすでに解説した通り、毒を塗った太鼓の音を聞くことによって煩悩が死ぬという法門、すなわち、法華経を誹謗したとしてもその縁によって、やがては成仏に至ること、逆縁の功徳を教える法理ですが、なるほどそのようなものか、それほど法華経に縁する功徳は大きいのかと納得できる方もいれば、法華経を誹謗した人がやがては成仏するというのは理解に苦しむと思われる方も
おられると思います。
折伏や仏法対話の中で法華経や信仰を否定し反発してきた人がむしろ成仏していくとは考えてみれば不思議な法理です。
まず一つ確認しておきたいことは、先ほどにも解説した通り法華経を誹謗の罪は最も重く、それは五逆罪をも上回る罪で気が遠くなるほどの長い時間地獄に堕ちるという大罪です。つまり法華経を誹謗してもやがては成仏するのだから何でも構わないと短絡的に捉えるべきではないということは確認しておきたい点です。
そのうえで、法華経誹謗の人がやがては成仏するとはどのような法理に則り実現されるのかを考えていきます。
そもそも私たちはなぜ法華経を受持することによって成仏することができるのでしょうか。その基本を掘り下げることによって逆縁による成仏の真実が見えてきます。
法華経、特に釈尊在世の仏法では、成仏するには3つの段階を経る必要があるとされています。ご存じの方も多いと思いますが、これは種熟脱の3つの段階においてそれぞれ利益をうける必要があるということです。
釈尊在世の衆生は法華経を聞くことにより成仏することができました。その理由は、釈尊によって久遠下種、つまり久遠の昔に下種されたことを種としてそこからさまざまな教えによって長遠な期間にわたり教化されてきたからです。
下種益、塾益、それぞれの利益を受けていたところに、最終的に法華経にて久遠実成の真実を知り、自らの中にある仏の生命を自覚することによって3つの利益をうけきり、成仏できるということになります。
しかし前置きしていた通りこれは釈尊在世の話であって、残念ながら私たちに当てはまる話ではありません。私たちには釈尊在世の衆生と同じように根本的には仏性が備わっているものの、それを触発する、釈尊による下種も長遠にわたる教化もありません。
これは私たち自身が明確に自覚するところです。
何よりも出発点となる下種がない私たちは、いくら素晴らしい教えを聞いても、長きにわたる修行をしても、一向に得脱、すなわち成仏することができないのです。それは成仏に至る3段階の利益が足りていないからです。
そこで末法に入りご出現になられたのが大聖人です。
大聖人によって法華経から南無妙法蓮華経という末法の仏種が顕されたことによって末法の衆生は成仏の道を開かれました。
そしてまた大聖人ご自身も南無妙法蓮華経によって仏に成られたために大聖人こそが久遠元初の自受用報身如来であるとされているのです。
しかしここで一つの疑問が浮かんできます。
大聖人によって下種益は完成されたものの、熟脱の功徳を得ていないのではないかと。ならばはやり3つの利益を満たさず成仏できないのではないかと。
しかしそこにこそ、逆縁による成仏が成立するヒントがあります。
結論から言えば、南無妙法蓮華経には、下種益がそなわると同時に、一瞬の生命の中に、種・熟・脱のすべての過程が具わるがゆえに、
南無妙法蓮華経を唱えたその一瞬の生命に3つの利益が満たされて即身成仏することが可能になります。
そして南無妙法蓮華経にどのように熟益、脱益が備わっているのか、
そのことを理解することが重要です。
即身成仏がなぜ可能となるかは様々な法理から説明することができますが、
今回は相対種という概念からその理由を解説していきます。
御書の世界で池田先生は次のように解説されています。
下種益の法が必要になってくるのです。煩悩・業・苦の三道に深く迷う末法のどんな凡夫に対しても、
直ちに仏種を植え、仏性を触発していける教法です。
それは、煩悩・業・苦の三道に迷う凡夫の生命にそのまま、
仏の法身・般若・解脱の三徳を開くことができる教法です。
仏界の生命と相対立するような煩悩・業・苦に迷う生命も仏種になりうるのだと説くのです。
これを「相対種」といいます。
大聖人は「始聞仏乗義」で、「相対種とは、煩悩と業と苦との三道、その当体を押さえて
法身と般若と解脱と称する、これなり」(新版御書一三二六㌻)と仰せです。
「その当体を押さえて」とは、煩悩・業・苦の三道に迷う当(とう)の生命を離れることなく、
その生命に法身・般若・解脱の三徳を現しうるという意味です。
御書の世界
加えて始聞仏乗義の御書講義の中では次のようにおっしゃられています。
凡夫の迷いと苦しみの生命それ自体がそのまま究極の真理を体とする仏の生命それ自体としての法身に、凡夫の生命を煩わし悩ます種々の精神作用としての煩悩・三惑がそのまま仏の智慧としての般若に、煩悩を因として起こす五逆・十悪等の業はそのまま仏の慈悲の自在なる振る舞いとしての解脱に止揚されるのである。
始聞仏乗義の御書講義
つまり煩悩・業・苦の三道がただ成仏のきっかけとして働いているのではなく、それ自体が、仏の真理、仏の智慧、仏の慈悲となるということになるのです。逆にとらえれば、日蓮大聖人の下種仏法においては、煩悩・業・苦を消滅させようとすることは、成仏の因を消し去ってしまうことになり、
いわば、その煩悩・業・苦の働きこそが、釈迦仏法でいう長遠な期間の修行によってえられる熟益に近い働きをし結果として成仏していけるということになります。
ここまでくると法華経誹謗する人がなぜのちに成仏する逆縁が起こるのかという点もその理由が明らかになってきたと思います。
法華経を誹謗することとはすなわち自他の生命に仏性を見出せないということであり、またこれまでの自分の誤った考えに執着してしまうなど、いわば迷いの生命により起こると言えます。そしてこれまでの解説からこのことをとらえていけば、むしろ法華経を誹謗するという迷いの生命が明確にあるからこそ、その人は成仏を確信していけるのです。
その観点からとらえるならばたとえ法華経を誹謗して長遠の時を地獄で送ることになってしまった人でさえ、その心に絶対悪は存在せず、南無妙法蓮華経を説き聞かせたその瞬間からすべての迷いや悪の意味が直ちに転換し、成仏に向けた生命の大転換のうねりがはじまるということになります。
そして南無妙法蓮華経を一度でも聞いたという事実がある限り、その流れは二度と再びとまることはありません。
祈りの中でこの人にこそ幸せになってほしいその思いで頭に浮かんだ人の中には、毒鼓の縁の法理から見れば、南無妙法蓮華経によって仏になったあなたとの出会いを通してすでに生命の大変革が始まっているとも言えます。
法理に照らして「あの人の幸福な人生を」との祈りが外れることは絶対にありません。
そして、祈らせてくれたその人こそがあなたを仏たらしめた仏であること気づき、
そこから感謝と報恩の対話が自然とひらかれていくのです。
以上、深堀ポイントを参考にしながら研鑽していただき
今月の座談会御書、法華初心成仏抄を拝読していきたいと思います。
もっと教学にJOINして教学を楽しく深めよう!
サイトを見てみるもっと教学とは?
本サイトは創価学会での教学をより一層深めるためのサイトです。
人間革命や御書、その他教学に役立つ書籍のチェックリストや感想を投稿できます。
読了チェックシート
読了した本やチャプターを簡単に記録し、進捗を管理できます。
感想を投稿・シェア
読んだ御書や人間革命について感想を投稿できます。
題目カウント
毎日の唱題・勤行の記録ができます。ホーム画面で全国の合計題目数も見られます!
研鑽バッジ
研鑽の進捗や日々の研鑽状況に応じてバッジを付与します。
拍手機能
素晴らしいと思った活動に拍手をおくることができます。