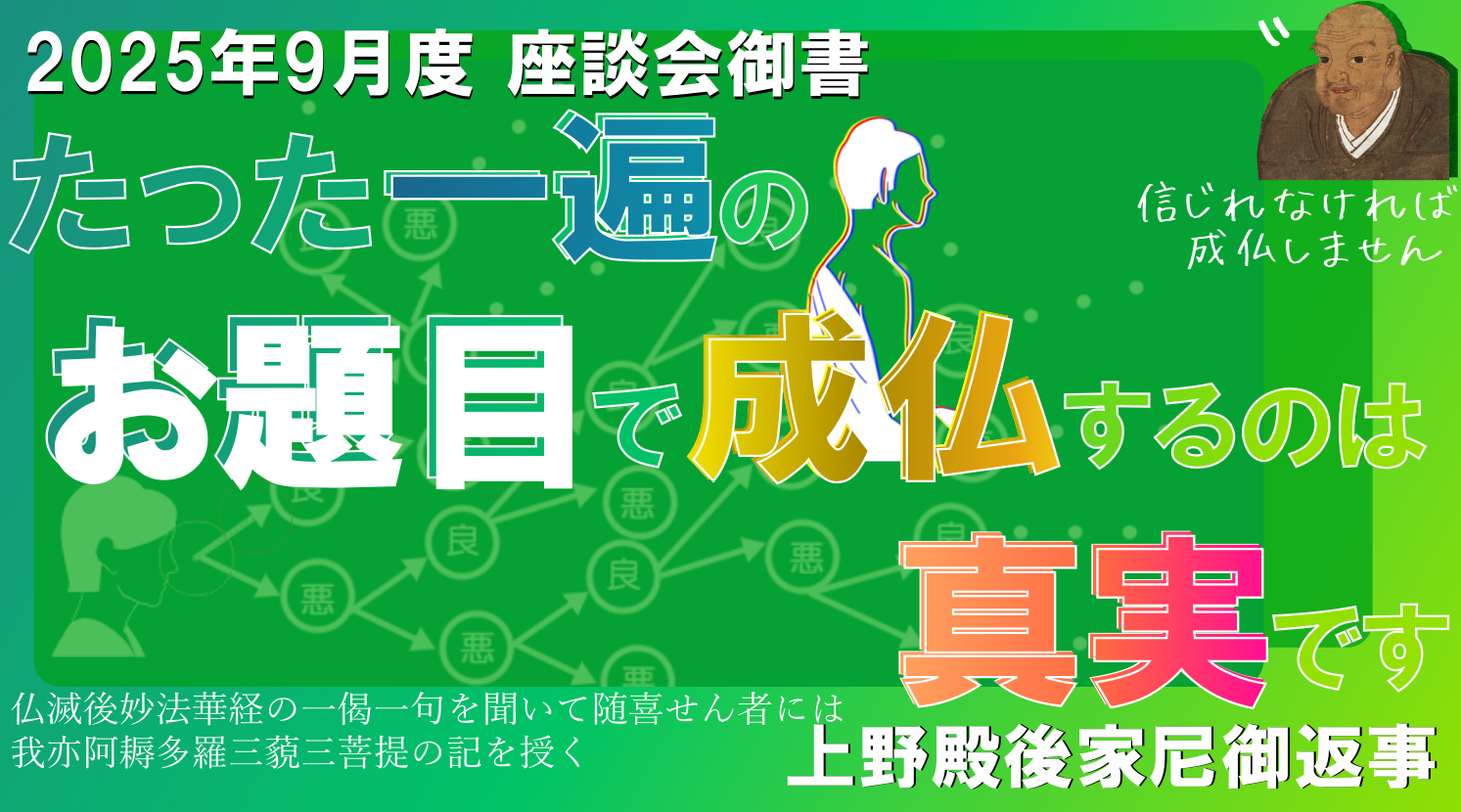
2025年9月座談会御書 上野殿後家尼御返事
みなさん、こんにちは
9月度の座談会拝読御書は、上野殿後家尼御返事です。
それでは今月も元気に学んで参りましょう!
内容は下記動画のスクリプトとなっております。
拝読御文
法華経の法門をきくにつけて
なおなお信心をはげむを、
まことの道心者とは申すなり。
天台云わく「従藍而青(藍よりして、しかも青し)」云々。
この釈の心は、あいは葉のときよりも、
なおそむればいよいよあおし。
法華経はあいのごとし。
修行のふかきはいよいよあおきがごとし。
通解
法華経の法門を聞くたびに、
ますます信心に励んでいく人を、
真の求道の人というのである。
天台は「青は藍から出て、藍よりも青い」と述べている。
この言葉の意味は、植物の藍は、
その葉からとった染料で重ねて染めれば、
葉の時よりも、ますます青みが深まるということである。
法華経は藍のようなもので、
修行が深まるのは、
ますます青くなるようなものである。
全 1505ページ 8~10行目
新 1834ページ 1~4行目
背景と大意
本抄は文永2年(1265年)7月10日、日蓮大聖人が44歳の時にあらわされたお手紙です。
御書全集では文永11年53歳での御述作とされていましたが、
御書新版においては、文永2年とされています。
今回の解説においては、最新の大白蓮華の解釈に沿ってすすめます。
文永2年と言えば、大聖人が伊豆流罪の赦免後、鎌倉に戻られた後で
松原にて東条景信に襲撃された小松原の法難の翌年ということになります。
本抄の対合衆は、駿河国、現在の静岡県中央部、富士上方上野郷門下の上野殿後家尼です。
上野殿後家尼は、有名な南条時光の母であり、また南条兵衛七郎の妻であった人物です。
女手一つで、9人の子を育て、後に活躍した南条時光に代表されるように一家で純真な信心を
貫き継承した門下としても知られています。
本抄をおくられた年の3月に
夫の兵衛七郎を亡くし、後家つまり未亡人となっています。
本抄は、亡き夫の追善供養のためにご供養の品々を大聖人に送られたことに対する
御返事となっています。
本抄ではまず、亡き夫は上野尼を仏法に導いた人であるから
間違いなく仏であり、生きていても死んでいてもそれはわからない
それが即身成仏という法門であると仰せになられます。
浄土や地獄などは本来、ただ我らの胸中にあるものであり、
そのことを覚知した存在が仏であり、それがわからないものを凡夫といい
またこのことは、釈迦仏をはじめとる諸仏が定めたことであるとご断言になられます。
また亡き夫兵衛七郎は法華経の行者であったので、
法門に照らして、法華経以外を信じ、法華経を受持しようとしない人や
法華経誹謗の人々がおちる地獄を免れていると仰せになられます。
上野尼においても、この法門をきいてよりは、従藍而青の言葉のように、
藍で青を重ねていくように、ますます信心に励んでいかれるよう
激励されます。
最後に、夫兵衛七郎は、法華経の行者だったのであり、
その即身成仏は疑いようがなく、その夫の死について嘆かれることもあるだろうが、
心の及ぶ限り追善供養をつくしていかれるがよいと励まされ本抄を結ばれています。
拝読箇所の解説
法華経の法門をきくにつけて
なおな信心をはげむを、
まことの道心者とは申すなり。
この法華経の法門というのは、具体的には、地獄即寂光の法門です。
浄土や地獄というものは、本来胸中にあり、
それを覚知する者が仏、そうでないものを凡夫と呼ぶ
そしてそれを覚知できるのは法華経であると仰せです。
そしてその仏がいる場所こそが、仏国土なのであるから、
たとえ地獄のように思われる場所であっても、
一たび浄土も地獄も我が胸中にありと自覚する仏がいれば、
そこは即寂光土、すなわち、地獄即寂光なのであると仰せなのです。
天台云わく「従藍而青(藍よりして、しかも青し)」云々。
この釈の心は、あいは葉のときよりも、
なおそむればいよいよあおし。
法華経はあいのごとし。
修行のふかきはいよいよあおきがごとし。
この法門を聞いたならばますます信心に励んでいきなさいと仰せのあと
それは、従藍而青すなわち、藍で重ね染めれば、ますます青が深まっていくような
ものだと仰せです。
法華経が藍なのであり、法華経を実践、修行することは、
色を重ねて、ますます青が深まっていくということであると仰せです。
深堀ポイント
これから御書を研鑽される方のために、深堀していきたいポイントを確認していきます。
今回の深堀ポイントは、
なぜ修行を深める必要があるのかという点です。
本抄に於いては、従藍而青の言葉の意味を通して、
ますます信心に励み、修行を重ねる人こそまことの道心者とは申すなりと仰せの通り、
信心のたゆみない継続の大切さを強調されておられます。
また本抄以外に於いても、信仰の「継続」がいかに大切であるかを仰せの御文は数多くあります。
そもそも、今の時、法華経を信ずる人あり。
あるいは火のごとく信ずる人もあり、あるいは水のごとく信ずる人もあり。
聴聞する時はもえたつばかりおもえども、とおざかりぬればすつる心あり。
水のごとくと申すは、いつもたいせず信ずるなり。
これは、いかなる時も、つねはたいせずとわせ給えば、
水のごとく信ぜさせ給えるか。とうとし、とうとし。
水火二信抄
しかし一方で
聖愚問答抄などにおいては、
一遍此の首題を唱へ奉れば一切衆生の仏性が皆よばれて爰に集まる時我が身の法性の法報応の三身ともに・
ひかれて顕れ出ずる是を成仏とは申すなり
聖愚問答抄
との御文などにもある通り、一遍のお題目や法華経に帰依するわずかな行動にも
無限の功徳があるとされ、そのことにより私たちは成仏していけると仰せの御文もあります。
これらの御文はどちらも何度も様々な御文で強調されていることであり、
どちらが本当の主張であるなどと甲乙つけられるものではありません。
しかし一見この2つの法理は矛盾しているのではないか、どちらが正しいのだろうと困惑している人も多いのではないでしょうか
具体的に言えば、
一遍の題目やわずかな法華経帰依の行動でも成仏するのであれば、
何度も塗り重ねる必要がないのではないかと、
また一方で、信心をますます重ねていくことが真の信仰者の証ならば、
わずかばかりの行動では足りないのではないかということです。
しかし、この二つの真理を矛盾していると感じてしまうその奥底には、
大きな思い違い、誤った生命観、成仏観が潜んでいる可能性を示唆しています。
それは成仏こそが最終的なゴールであり、成仏が果たされればすべて無事終了であるという思想です。
たしかに仏法の目的とは成仏していくことであって、
それは大聖人が世雄御書にて
日蓮は少きより今生のいのりなし。ただ仏にならんとおもうばかりなり
世雄御書
と仰せの通り、大聖人ご自身も、修行と仏法の実践の目的は、仏の境涯に至るためのものであると
ご断言になられています。
しかし一方で、本抄で仰せの通り、
成仏とは何か特別な存在へと昇格していくことではなく、
夫れ浄土と云うも地獄と云うも外には候はず・ただ我等がむねの間にあり、
これをさとるを仏といふ・これにまよふを凡夫と云うと仰せの通り、
自らの中に本来仏の生命があることを覚知することが仏であるともご断言です。
すなわちこれらのことを矛盾なく解釈するならば、
私たちが持つべき成仏観とは、
いつか仏になれる日を目指してどこまで続くのかわからない長い道のりに
歩みを進めていくということではなく、すでに自らの中にある仏の生命をいかに覚知し開いていくか、開き続けていくか
このことの一瞬一瞬、今この時の勝負であるということです。
仏と魔との闘争もまた同様です。
長い人生、まじめに信仰し懸命に生きていくにあたって
難の存在は避けては通れません。
それは御文にもある通りです。
行解既に勤めぬれば、三障四魔、紛然として競い起こる乃至随うべからず、
畏るべからず。これに随えば、人を将いて悪道に向かわしむ。これを畏るれば、正法を修することを妨ぐ
兄弟抄
人間関係、仕事上の困難、病気、肉親や大切な友の死など
人生には数々の困難があります。自らの失策や油断、慢心によって転落していくこともあるでしょう。
人生にはいわゆるターニングポイントと言える転換点があり、それらを節目として
人生が良い方向や悪い方向に転じていくように見えます。
しかし、それらの大きな移り変わり一つ一つについて解像度を高めて見ていくと
それは結局一瞬一瞬変化する前進と後退の繰り返し、すなわちより良い方向に進みたい自分と
それを阻もうとする自分自身に巻き起こる瞬間瞬間の闘争であると言えます。
環境の変化によって引き起こされる困難はあります。しかしそれをうけて自分はどのような志で
何をするのかという点は、まぎれもなく自分の中にある闘争といえるでしょう。
池田先生は次のようにおっしゃられています。
正義の前進が勢いを増せば、
反動の魔も、当然、競い起こる。
ゆえに、一日一日、
一瞬一瞬に勝負がある。
「今」を勝つことが、
一切の勝利の出発点である。
2019年7月20日 四季の励まし
一遍のお題目には、無量無辺の功徳があります。
それは別の御書南条殿御返事(百箇日御書)で
南無妙法蓮華経を只一度申せる人・一人として仏にならざるはなし
南条殿御返事
と大聖人が仰せの通りです。
題目には直ちにあなたの心に仏性を拓く絶大な功徳がある。
そしてまた、仏法は仏と魔との永遠の勝負でもある、
私たちの生命は可能性を閉ざす不信に日々覆われそうになりながら、
懸命に自他の生命の可能性を信じようと戦っているということです。
魔との勝負があってはじめて仏である、不可逆的でいかなる魔も起こらない境涯などというものは存在せず、
それはもはや人間でもなく、もちろん真実の仏の姿でもありません。絶対的幸福境涯の絶対とは境涯の不可逆性を説いたものでないのです。
従藍而青、仏の境涯は何度も塗り重ねて、日々深めていくものである。
法華経すなわち南無妙法蓮華経を唱え広めることで日々仏道修行が生命に刻まれ、日々仏に成っていく
そしてまた、たった一度のお題目の功徳が広大無辺ということはすなわち、
自身の生命の可能性を一瞬でも信じようとすることがいかに尊い功徳によってなされ、得難いことなのかを示しています。
これが法華経で釈尊があらわした真実の成仏観であり、すなわち日蓮仏法の生命観、成仏観です。
先月の大白蓮華のfactに紹介されていた鳥取の同志の記事に心に残る言葉がありました。
「屈しないこと、それがすべてです」
たとえ挫折の連続であっても、何度も何度も立ち上がり続ける。
仏とは別名「能忍」と言われ、それはよく耐え忍ぶことを意味します。
不屈の生命こそが仏の異名であり、そのことこそが大聖人の生涯求められた成仏です。
藍染された生地には一つとして同じものはなく、その染め方や愛用した年月、その人の生き方が
そこに色や風合いとして現れてくると言われています。
私たちの信仰もまた同じであり、同じ信仰だから同じような人間になっていくのではありません。
それぞれの特徴を生かしながら、その人独自の魅力を表現し、花開かせていく。
そしてその輝きの根本には、自他ともの幸福を追求し懸命に生きていく尊い姿があります。
藍の花言葉は「あなた次第」です。
あなたの生命には、久遠の昔から、未来永劫に渡って、変わらず仏の生命が常住し続けています。
あなたの輝く未来を拓くカギは、この可能性を信じるか信じないか、あなたの真の信心、その一点にかかっているのです。
それを拓いていく力は
あなたがどのような人生を歩んでいくのか
全ての宝が本当に自らの中にあるのかないのか、あなたの生命をどのように輝かせていくのか
そのすべてはあなた自身が自ら決めていくことなのです。。
もっと教学にJOINして教学を楽しく深めよう!
サイトを見てみるもっと教学とは?
本サイトは創価学会での教学をより一層深めるためのサイトです。
人間革命や御書、その他教学に役立つ書籍のチェックリストや感想を投稿できます。
読了チェックシート
読了した本やチャプターを簡単に記録し、進捗を管理できます。
感想を投稿・シェア
読んだ御書や人間革命について感想を投稿できます。
題目カウント
毎日の唱題・勤行の記録ができます。ホーム画面で全国の合計題目数も見られます!
研鑽バッジ
研鑽の進捗や日々の研鑽状況に応じてバッジを付与します。
拍手機能
素晴らしいと思った活動に拍手をおくることができます。