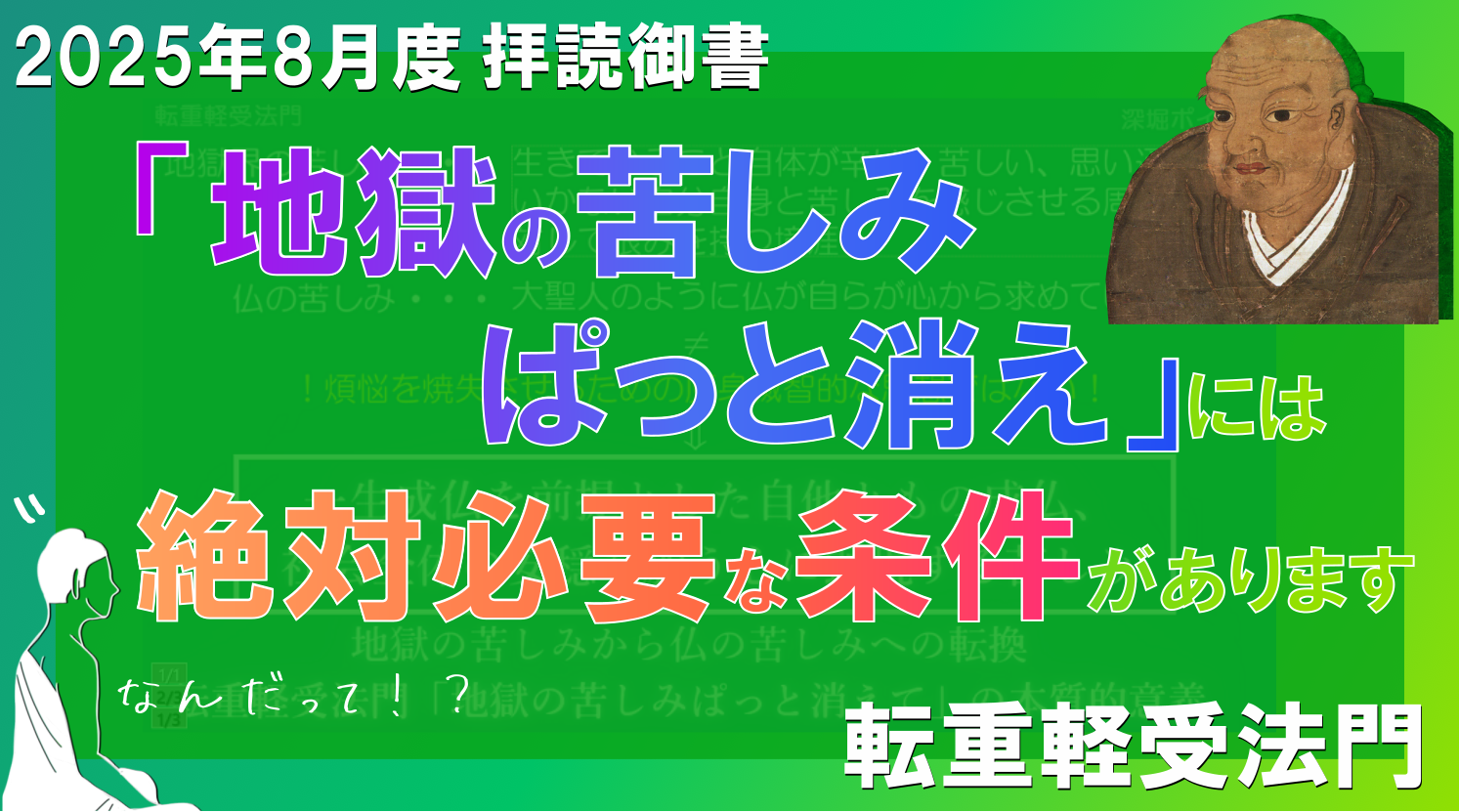
2025年8月拝読御書解説 転重軽受法門
YouTubeにアップしている御書講義、解説の内容をこちらに書き起こしさせていただきます。文字で読みたい方はぜひご覧ください。
※動画編集作業の都合上、YouTube音声と以下の文章で多少表現が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
拝読御文
涅槃経に転重軽受と申す法門あり。
先業の重き今生につきずして、
未来に地獄の苦を受くべきが、
今生にかかる重苦に値い候えば、
地獄の苦しみぱっときえて死に候えば、
人天・三乗・一乗の益をうること候。
全 1000ページ 3~4行目
新 1356ページ 3~5行目
通解
涅槃経に「転重軽受(重きを転じて軽く受く)」
という法門がある。
過去世でつくった宿業が重くて、
現在の一生では消し尽くせず、
未来世に地獄の苦しみをうけるはずであったものが、
今世において、このような(法華経ゆえの大難という)
重い苦しみにあたったので、
地獄の苦しみもたちまちに消えて、
人・天の利益、
声聞・縁覚・菩薩の三乗の利益、
そして一仏乗の利益たる成仏の功徳を得るのです。
背景と大意
本抄は文永8年(1271年)10月5日、日蓮大聖人が50歳の時に流罪により佐渡に出発する前、一時的に相模国依智に留め置かれた際に大聖人のもとを訪れた門下に対してあてられたお手紙です。
対合衆は下総国の中心的な役割をになっていた3人の門下、大田乗明、曽谷教信、金原法橋です。
当時大聖人は、人生で最大の大難の渦中にあり、このお手紙の前月には、竜の口の法難に遭われていました。
竜の口では、光り物(彗星や火球、球電現象ではないかと言われています)の出現により刑の執行が中止となりましたが、
すぐさま当時死罪にも匹敵するとされた佐渡流罪が執行されることとなります。
本抄はその佐渡流罪の直前に認められたものであり、まさに大聖人と難との戦いが最も激しい時期におけるご境涯を顕されたものと言ってよいでしょう。
本抄ではまず、すりはんどくの故事を通して、心を同じくする三人のうち一人でも大聖人のもとに来たのであれば、
これは三人で来たのと同じであると仰せになられます。
つづいて転重軽受の法門について仰せになれます。
過去の宿業ゆえに、現在にその苦しみをうけ、さらに未来に渡って地獄の苦しみを受けるところが、法華経ゆえの大難に遭うことによって
その苦しみが消え、最終的には一仏乗を得ていくことができると仰せになられます。
大聖人や過去の正法の行者が難に遭った理由については、まず第一に過去の罪業のゆえ、
そして第二には、法華経を広めるその時々、場所に誤った教えや思想により命の濁った人々が
満ちている中にあって折伏を実行するからであると仰せです。
そして、法華経を読むだけでなく実践することは難行であり、末法に於いては大聖人ただお一人が法華経を身で読んでいるとご断言になられます。
最後に、大聖人が命の危機に遭ってもなおこの正法を広めようとするのは、
自らの成仏のみならず、国の安穏を思ってのことであるとの大慈悲を示され本抄を結ばれています。
拝読箇所の解説
涅槃経に転重軽受と申す法門あり。
先業の重き今生につきずして、
未来に地獄の苦を受くべきが、
今生にかかる重苦に値い候えば、
地獄の苦しみぱっときえて死に候えば、
人天・三乗・一乗の益をうること候。
今回の拝読箇所は、転重軽受の法門についてのべられる箇所です。
先業といのは、過去世に自らが犯した罪であり本抄においては、不軽菩薩の例をとおして、その罪は、正法を誹謗したことによって作られていると仰せになられます。
正法誹謗は、謗法と言われ、五逆罪を超える、仏法上でもっとも重い罪であるとされています。
この過去世の大罪にもとずき、現在苦しみ、そして未来に渡っても苦しみ続けるところを法華経ゆえの大難に遭うことにより、その宿業を消していくことができるということです。
そして最終的には、その罪を消すことだけにとどまらず、一仏乗、すなわち法華経の利益をうけて成仏していくことができるということです。
これが転重軽受の法門です。
深堀ポイント
これから御書を研鑽される方のために、深堀していきたいポイントを確認していきます。
今回の深堀ポイントは、
地獄の苦しみがぱっと消えるとはどういうことかという点です。
今回の拝読箇所の中でも特に有名な一説は、地獄の苦しみぱっと消えての箇所かと思います。
様々なご指導、そして日々の活動、友の激励の際にも引用したことがある人は多いのではないでしょうか。
信心を貫いていけば、今の苦しみがぱっと消える時が来るからと励ましを送られた方もいるかと思います。
しかし一方で、苦しみの渦中の人にとっては、今の苦しみがぱっと消えるとはどういうことか
祈っているのに苦しみは消えてない、そんなことはあり得ないとの実感を持っている人も
少なからずいるかと思います。御文であるから否定はできないものの自分はそのような
感覚がないと思う人もおおいのではないでしょうか。
なぜ地獄の苦しみぱっと消えると仰せになったのか
本抄において大聖人が「地獄の苦しみぱっと消えて」と言われたのはなぜでしょうか。
ご執筆の背景を再度確認すると、ご執筆当時はまさに、竜の口にて処刑台に立たされ、その刑の執行は失敗に終わったものの、その次には死罪にも等しいとされる佐渡流罪が執行される直前です。
佐渡流罪の日を待つために一時的に預けられた本間氏の屋敷で、大聖人はどのような御心境でいらしたのでしょうか。
大聖人は流罪の日までを過ごす依智に滞在中、本抄、転重軽受の法門をいれて5つのお手紙を門下に送られています。
その中で転重軽受の法門以外に残された代表的な御文を2つ見てみましょう。
竜の口の法難の2日後、9月14日、富木常忍に対して
御嘆きはもっともであるが、自分としてはもとより覚悟していたことであるからいまさら嘆いてはいない。今まで頚を切られないでいることこそ残念に思っている。法華経のために過去世にもし頚を切られていたら、今生にこうした少身の身は受けなかったであろう。また経文には数数見擯出と書かれており、法華経のためにたびたび御勘気をこうむることによって過去の重罪をけしてこそ、仏になれるのであるから、我と我が心から求めて苦行をしているのである。
土木殿御返事
その約2週間後、10月3日 法難により牢屋に入れられた門下に対して
あなた方は法華経一部を身で読まれているのであるから、その功徳はわが身並びに父母・兄弟の生者と死者のすべてに、廻向されることであろう。今夜の寒さにつけて、ますますわが身よりも牢中のあなた方のことが思いやられて、心の苦しみは申しつくせない。牢を出られたならば明年の春かならず佐渡へおいでなさい。お会いしましょう。
五人土篭御書
自らが死罪にも等しい刑の執行を前にしても、その信念、ご覚悟は全く揺るがず、むしろ寒い夜に、牢に繋がれた弟子たちのことを思い苦しい思いをしているとのご心情を述べられています。
特に9月14日のお手紙については、今まで首を斬られないでいることを残念に思っている、我が心から求めて苦行をしているのであると仰せです。
大聖人が弟子に対してこの転重軽受の法門、特に地獄の苦しみぱっと消えての一説をお示しになられたその理由は、
単に、絶体絶命の状況であっても信仰を貫いていけば、地獄の苦しみがぱっと消えることになっている、理論上そうなるはずだという説明にとどまらず、大聖人が今まさにこの時に、かつて不軽菩薩がそうであったように、法のために迫害にあって、そのうえで、大聖人のご心情の中から実際に「地獄の苦しみ」が消えたからこそ、そのことを弟子たちに宣言していると思えてきます。
そのご心情とは、決して目の前の苦しみがなくなったわけではない、それは大聖人も苦行と表現されていることからわかります。
しかし、その苦しみをも上回る大きく雄大なご境涯で悠然と見下ろされている。むしろ心から求めて苦しみをうけている、そして弟子を思い、その状況に心を砕かれている。もはやそこには「地獄の苦しみ」というものではなく、いわば「仏の苦しみ」ともいうべきものが顕現されていると思えてなりません。
仏法の目的、仏に成るとは苦しみを消滅させることではありません。それは竜の口の法難にて、大聖人が発迹顕本されてもなお、これは苦行であると仰せになられていることからも明らかです。しかし地獄の苦しみ、いわば地獄界の苦しみは断ち切っていくことができる。
地獄界の苦しみとは、生きていること自体が辛い、苦しい、思い通りにいかない自分自身と苦しみを感じさせる周囲に対して恨みを持つ境涯です。
そして仏の苦しみとは、大聖人のように自らが心から求めている苦しみと言えます。もちろんそれは、煩悩を焼失させるための灰身滅智的な思想ではなく、一生成仏を前提とした自他ともの成仏、そして大聖人のように社会全体の安穏を願う心に顕現する苦しみです。
この地獄の苦しみから仏の苦しみへの転換こそが、転重軽受の法門に説かれた地獄の苦しみぱっと消えての本質的な意味なのかもしれません。
池田先生は次のようにご指導くださっています。
苦難がないことが幸福なのではない。苦難に負けず、たとえ倒れても、断じて立ち上がり、乗り越え、勝ち越えていくところに、人生の真の幸福があり、喜びがある。
現実の生活は、さまざまな行き詰まりとの戦いである。しかし、何が起ころうと、決して悲観することはない。一歩、深くとらえれば、全てが信心の試練であり、さらなる幸福への、成仏への転機であり、チャンスなのである。
悩んだ人ほど偉大になれる。つらい思いをした人ほど、多くの人を救っていける。偉大な使命がある。これが仏法だ。菩薩道の人生である。
今、直面している困難は、信心の眼で見れば、自ら願った使命である。そう確信して前進することが、「誓願の祈り」の証しだ。
仕事のこと、経済苦、人間関係の悩み、病気の克服など、目下の課題に打ち勝つために、猛然と祈ることだ。
自分自身が、断固として勝利の実証を示していくことが、同じような苦しみに直面する友を励ます光となる。
今の労苦に何一つ、無駄はない。厳しい冬の試練があるからこそ、爛漫と咲き誇る勝利の春が必ず来るのだ。
試練の冬越え 花よ咲け
目の前の苦しみ、これをただ自分のことととらえれば、それは単なる苦しみであり、こじらせば地獄の苦しみへと堕ちていきます。
しかし一たび友のため、社会のため、今自分のかかえる苦難があると捉えれば、それはたちまち希望のエネルギー源となり、地獄の苦しみぱっと消え、自他の未来を拓く創造的な苦難となります。
友を思い、苦しみの意味を善の方向へと転じていくこと。このことがどんなときにも希望を見失わない、日蓮仏法の根幹をなす哲学です。
そしてそれはたとえ自らの死を目の前にした究極の状態であったとしても、それでも誰かのために生きようとする南無妙法蓮華経の生命から躍動するのです。
以上、深堀ポイントを参考にしながら研鑽していただき
今月の座談会御書、転重軽受法門を拝読していきたいと思います。
もっと教学にJOINして教学を楽しく深めよう!
サイトを見てみるもっと教学とは?
本サイトは創価学会での教学をより一層深めるためのサイトです。
人間革命や御書、その他教学に役立つ書籍のチェックリストや感想を投稿できます。
読了チェックシート
読了した本やチャプターを簡単に記録し、進捗を管理できます。
感想を投稿・シェア
読んだ御書や人間革命について感想を投稿できます。
題目カウント
毎日の唱題・勤行の記録ができます。ホーム画面で全国の合計題目数も見られます!
研鑽バッジ
研鑽の進捗や日々の研鑽状況に応じてバッジを付与します。
拍手機能
素晴らしいと思った活動に拍手をおくることができます。