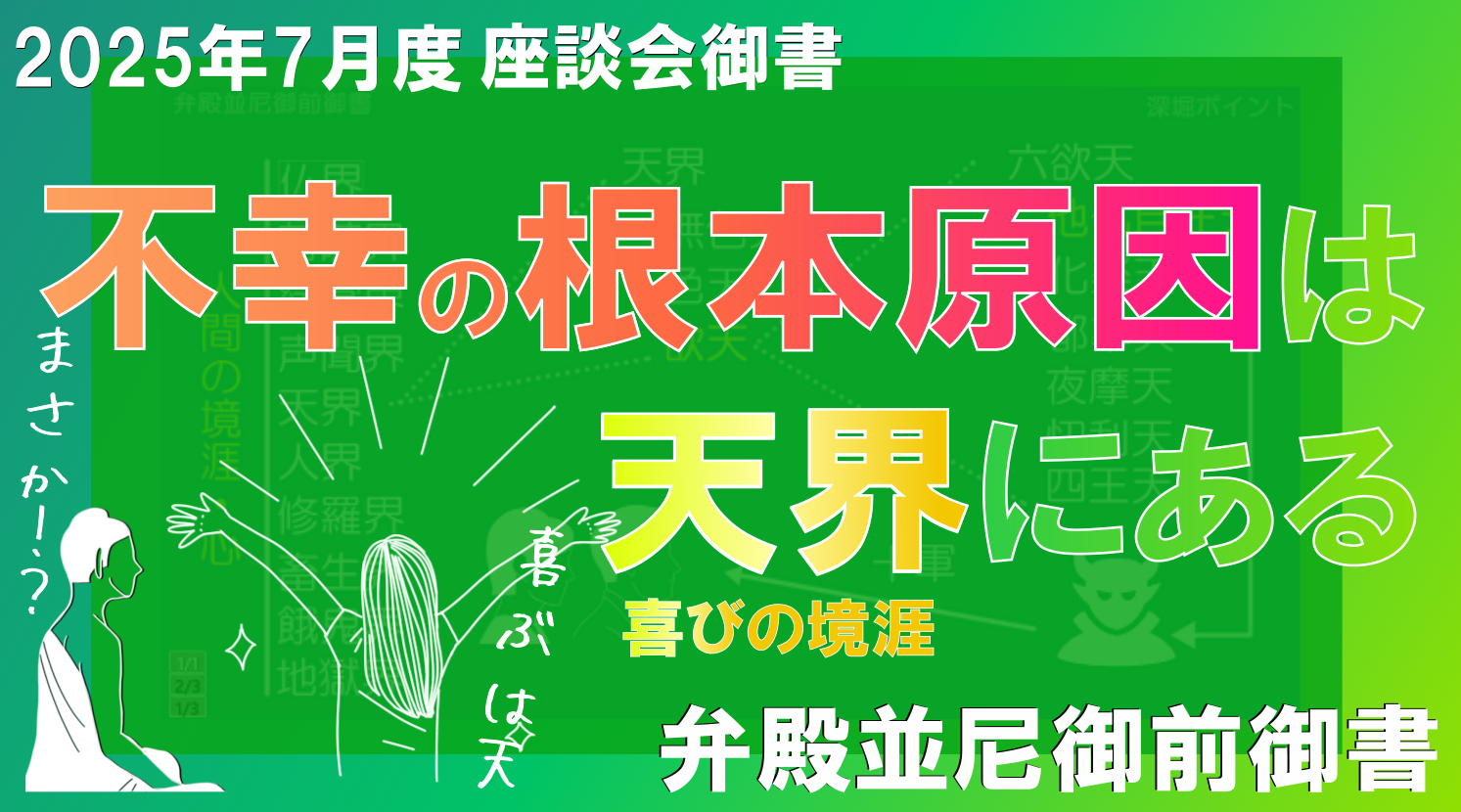
2025年7月座談会御書解説 弁殿並尼御前御書
YouTubeにアップしている御書講義、解説の内容をこちらに書き起こしさせていただきます。文字で読みたい方はぜひご覧ください。
※動画編集作業の都合上、YouTube音声と以下の文章で多少表現が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
拝読御文
第六天の魔王、十軍のいくさをおこして、
法華経の行者と生死海の海中にして、
同居穢土を、とられじ、
うばわんとあらそう。
日蓮その身にあいあたりて、
大兵をおこして二十余年なり。
日蓮、一度もしりぞく心なし。
全 1224ページ 3~5行目
新 1635ページ 1~3行目
通解
第六天の魔王は、十種の魔の軍勢を
用いて戦を起こし、
法華経の行者を相手に、
生死の苦しみの海の中で、
凡夫と聖人がともに住んでいるこの
娑婆世界を“取られまい”“奪おう”と
争っている。日蓮は、
その第六天の魔王と戦う身に当たって、
大きな戦を起こして、二十数年になる。
その間、日蓮は一度も退く心はない。
大白蓮華2025年7月
背景と大意
本抄は文永10年(1273年)9月19日、日蓮大聖人が52歳の時に佐渡の一谷(いちのさわ)で著された御書です。
対合衆については、題号に「弁殿並尼御前御書」とあり、その内容は主に弁殿すなわち弟子の日昭に関わりのある尼御前にあてられたものと考えられています。
大聖人への数々の難、そして本抄をご執筆になられた当時は大聖人以外への迫害も激しく起こり、多くの門下が退転している時代でした。
本抄の内容
本抄では、過去のいかに優れた武将であっても、数年、十数年後には敗れるという史実と対比して、大聖人は、民衆が苦しむ娑婆世界にあって、第六天の魔王との戦いをおこしてもう二十余年になり、一度も退くことがなかったと仰せになられます。
そして多くのものが退転する中にあって尼御前は信心を貫かれたことをご賞賛になられます。
最後に、尼御前自身の召使を大聖人につけたことは、必ず釈尊、多宝をはじめとする
諸仏が知るところであると仰せになられ本抄を結ばれています。
拝読箇所の解説
第六天の魔王、十軍のいくさをおこして、
法華経の行者と生死海の海中にして、
同居穢土を、とられじ、
うばわんとあらそう。
この第六天の魔王が、十軍のいくさを起こすとは、大智度論にしめされた
十種類の煩悩が信心を阻むことを示しています。
十種類の煩悩とは、
①欲②憂愁(憂うこと)③飢渇(飢えと渇き)④渇愛(妄執)⑤睡眠⑥怖畏(怖れること)⑦疑悔(疑いや悔い)⑧瞋恚(怒り)⑨利養虚称(利を貪り、虚妄の名聞に執着すること)⑩自高蔑人(自らおごり高ぶり、人を卑しむこと)
のことです。
そしてその第六天の魔王と戦っているのは誰か、
それが法華経の行者です。
同居穢土と娑婆世界のことで、
地獄界から仏まで生死という根源的な摂理の世界で、
あらゆる人々が暮らす世界にあって、
第六天の魔王と、法華経の行者が戦っているのです。
日蓮その身にあいあたりて、
大兵をおこして二十余年なり。
日蓮、一度もしりぞく心なし。
そして法華経の行者である大聖人は二十数年間にわたり第六天の魔王と戦い
一度たりとも退く心はないと仰せです。
本抄のご執筆もまさに流罪中の佐渡であり、まさに戦いの真っただ中にあっての、烈烈たる気迫です。猛威を振るう魔との戦いの中にあっても、志同じくして戦うけなげな尼御前を最大限に支え励まし守ろうとする気迫、大慈悲が伝わってきます。
深堀ポイント
これから御書を研鑽される方のために、深堀していきたいポイントを確認していきます。
今回の深堀ポイントは、
大聖人が「退く心なし」との表現を用いられたのはなぜかという点です。
多くの御文を学習したことがある人にとっては、
全く違和感のない言葉かもしれませんが、考え方によっては、
魔に勝つや魔を破るという表現でも、御文の意味が通じるのではないかと感じられます。
二十余年は勝利の歴史であったとの表現であれば、痛快な勝利劇を想像し、
難に遭われているさなかに遭ってもこれこそが勝利の姿なのだ感じ仏法の真髄を感じ取られるかもしれません。
しかしそうではなく、大聖人は一度も退く心なしと表現された。
今回はあえて、御文の中でよく耳にする表現「退く心なし、の意味と意義を深堀していきたいと思います。
大聖人が退くことなく戦われたものとは、本抄でも学習した通り、
それは第六天の魔王との戦いです。
第六天の魔王については、御書の中にたびたび登場し、
特に重要な御書とされるものには必ず登場するいわばこの仏法の法理を語るうえでは
外すことのできない重要な要素であると言えます。
まさに第六天の魔王のことを語らずして、この仏法を理解することができないと言えるのではないでしょうか。
それでは第六天の魔王とはそもそもなんでしょうか。
それは信心を阻む存在であり、三障四魔や三類の強敵などあらゆる障魔の最も根源的なものとされています。
そして大聖人は兄弟抄の中で
此の法門を申すには必ず魔出来すべし魔競はずは正法と知るべからず
兄弟抄
と仰せになられています。
いわば私たちが信仰を貫いていくこととは、すなわちこの第六天の魔王との戦いを繰り広げていくことと同義であり、
逆に言えば魔との戦いのない正法はないということが言えます。
それでは第六天の魔王はどこからやってくるのか
それはその名の通り、第六天すなわち、
天界における欲天の最上とされています。
天界の欲天とは、欲望に囚われた衆生が住む世界であり、
衆生は、この欲界つまり地獄から天界の一部欲天までの六道を輪廻するといわれています。
第六天の魔王は、この欲天より顕れ十種の魔軍を率いて衆生を苦しめているということになります。
またそもそも天界とは人間の一つの境涯でもあります、
つまるところ、第六天の魔王は己心のあらゆる欲望を満たそうとする心に生まれてくるということになります。
魔王と言えば、何となく地獄の番人、地獄界から這い上がってくるというイメージを持っていましたが、
実際には喜びの境涯である天界に住んでいることに個人的に意外に感じられたと同時に、
それこそが仏法を阻む根源であるというのは、なるほど私たちが戦っているものとは
非常に厄介で気づきにくく最も手ごわい悪鬼であると言われることに
深くうなずいた方もおられるかもしれません。
ここで十種の魔の軍勢を改めて見てみると、人間というものは元来そういうものであるということも言えます。
生理現象などによってあらゆる欲が自然に生まれ、憂い、渇き、怒り、傲り、怖れ、利益を欲するそれこそが人間じゃないか、人間らしさと言われてみれば、そうなのかもしれません。
あの人にも人間らしいところがあるのかなどという言葉があるように、
その側面を見て、人を安心させるような要素があるのも事実と言えます。
このことから果たして第六天の魔王というもの、そして十種の魔の軍勢が絶対的に悪いものなのかという疑問もでてきます。
さらに深く考えていくと、十種の魔の軍勢を完全に制圧し、消滅させることなど果たしてできるのかと考えれば、
そのことはノーと言わざるを得ません。
十種の魔の軍勢の一つとされる睡眠をとってみても、それなくしては生命を維持することは不可能です。
むしろ仮に第六天の魔王そして十種の魔軍を天界より完全に排除することができたとしたらならば、
その人はもはや人間ではないと言えるかもしれません。
第六天の魔王は、法華経の行者の対峙するものであり仏法の広がり、成仏を阻む根源であり
しかしその一方で、その存在こそが人間を人間たらしめているものということも言えます。
最勝の経典である法華経、なかんずく日蓮仏法においては、凡夫だからこそ仏になれるのだと説きます。
『本仏と云うは凡夫なり 迹仏と云ふは仏なり』
諸法実相抄
つまり成仏という絶対的幸福境涯を目指す私たちは
凡夫だからこそ、成仏できるのであり、その条件の一つが
己心の天界に住む第六天の魔王ないしその手先である十種の魔軍であるということになります。
池田先生は常々、仏法は仏と魔との闘争であるとおっしゃられています。
すなわち仏と魔との闘争とは、
成仏しようとする自分と、
成仏を阻もうとする自分との闘争であるということができるのではないでしょうか。
そして重要なことは、第六天の魔王や魔軍その存在自体を否定し、消し去ってしまえば、
自分自身は凡夫ではなくなり、成仏の道が閉ざされてしまうということです。
己心に第六天の魔王がいるからこそ、私たちは成仏を果たすことができるのです。
それでは私たちは魔を心に飼い続けていれば成仏するのかと言えば当然そうではありません。
第六天の魔王のしたいままにするならば、人生はあらゆる欲にまみれ、制御を失い、奈落の底へと転落してしまいます。
これは個人を超えた集団や国家でも同じことが言えます。欲に支配された世界は、まっとうなルールを定めることができず
争い、奪い合い、だまし合う世界となります。
つまり第六天の魔王の存在を常に認めつつも、
その魔の軍勢が強く働き、心を支配しないようにするということが私たちの戦いなのです。
大聖人は治病大小権実違目で
「元品の無明は第六天の魔王と顕われたり」
治病大小権実違目
と仰せです。
第六天の魔王が蠢動する根本的な原因は、元本の無明、
自らをはじめ万物が妙法の当体であることがわからない、最も根源的な無知です。
つまり自他の心に仏性があると信じられない生命こそが
第六天の魔王の本質であり、その心によってあらゆる欲望に支配された姿となって表れていくということになります。
逆に言えば、仏性を信じ続けることが、唯一魔の軍勢を抑え成仏の道を開く方法なのです。
御義口伝には、
元品の無明を対治する利剣は信の一字なりと仰せのとおりです。
それは仏性の覚知こそが凡夫を仏たらしめる唯一の要素だからです。
池田先生は次のようにおっしゃられています。
凡夫は凡夫のままで仏なのです。
命に差別はない。
平等です。
平等に仏です。
違うのは、
それを自覚しているか否か、
その「心」の違いだけです。
法華経の知恵
大聖人がなぜ勝利や魔を破るなどという言葉を用いずに退く心なしとの表現をされたのか
その真意は大聖人のみぞ知ることです。
しかし、第六天の魔王と法華経の行者の戦い、その本質、根幹が
自他の生命にある仏性を信じるか信じられないかの勝負であると考えれば、
それは現実の争いごとのように、終わりがあって、ある時勝ち負けが決まるというものではなく、
永遠に続く自己との闘争だからなのかもしれません。
だからこそ勝つことよりも退かない心、このことを強調されたのではないでしょうか。
そして退かない、の言葉には、
仏性を覚知する心と同時に第六天の魔王の存在も認める
まさに仏に成るとはどういうことかを明確に言い表した言葉であると思います。
大聖人が本抄をご執筆になられたのは、佐渡流罪中であり
まさに第六天の魔王が大聖人とその門下を引き裂こうと猛威をふるうさなかのことです。
食べるものを奪い、着るものを奪い、住居を奪い、諸宗の僧侶や政府役人に取り入って、命をも奪おうとしましたが、
ついに第六天の魔王は大聖人の命と希望の炎を消すことができませんでした。
凄まじい難の嵐、愛弟子たちを苦しめられる苦悩にあい
ぼろぼろになっても、大聖人は叫ばれました。
日蓮、一度もしりぞく心なし。
この大聖人の烈烈たる気迫の大音声は、
『それでも一切衆生の仏性を信じ切る、信じ続ける』との大聖人の大慈悲です。
そして800年たった今もなお、絶対的幸福境涯とはいかなるものか
それは退かない心であると私たちに具体的に示し続けてくださっているのです。
もっと教学にJOINして教学を楽しく深めよう!
サイトを見てみるもっと教学とは?
本サイトは創価学会での教学をより一層深めるためのサイトです。
人間革命や御書、その他教学に役立つ書籍のチェックリストや感想を投稿できます。
読了チェックシート
読了した本やチャプターを簡単に記録し、進捗を管理できます。
感想を投稿・シェア
読んだ御書や人間革命について感想を投稿できます。
題目カウント
毎日の唱題・勤行の記録ができます。ホーム画面で全国の合計題目数も見られます!
研鑽バッジ
研鑽の進捗や日々の研鑽状況に応じてバッジを付与します。
拍手機能
素晴らしいと思った活動に拍手をおくることができます。