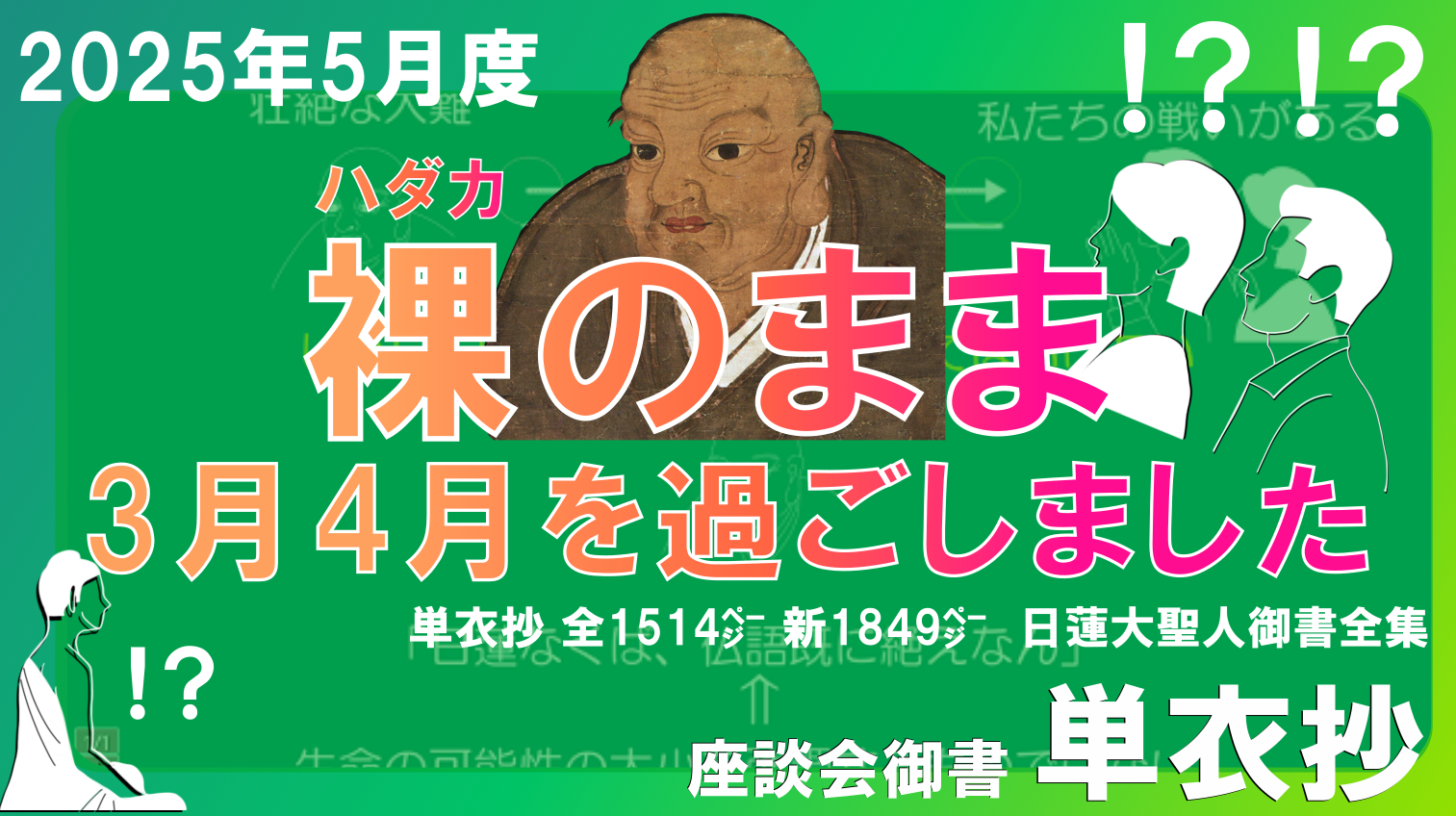
2025年5月座談会御書解説 単衣抄
YouTubeにアップしている御書講義、解説の内容をこちらに書き起こしさせていただきます。文字で読みたい方はぜひご覧ください。
※動画編集作業の都合上、YouTube音声と以下の文章で多少表現が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
拝読御文
日蓮、日本国に出現せずば、
如来の金言も虚しくなり、
多宝の証明もなにかせん。
十方の諸仏の御語も妄語となりなん。
仏の滅後二千二百二十余年、
月氏・漢土・日本に「一切世間多怨難信
(一切世間に怨多くして信じ難し)」
の人なし。
日蓮なくば、仏語既に絶えなん。
全 1514ページ 13~14行目
新 1849ページ 4~6行目
通解
日蓮が日本国に出現しなければ、
仏の金言も虚言となり、
多宝如来が
「法華経は真実である」と言った証明も、
何の役にも立たない。
十方の諸仏のお言葉もうそとなるであろう。
仏が亡くなられて二千二百二十余年の間、
インド、中国、日本に
「世間の人々に敵対者が多く、信ずることが難しい」
と説かれる経文通りに難に遭った者はいない。
日蓮がいなければ、仏の言葉は、
もはや途絶えてしまったことであろう。
全 1514ページ 13~14行目新 1849ページ 4~6行目の通解
背景と大意
本抄は建治元年(1275年)8月、日蓮大聖人が54歳の時に身延で著されました。
対合衆は、不明ですが、南条家縁(ゆかり)の鎌倉に住む夫妻であったと推察されています。
本抄で大聖人が言及されていますが、本抄をあてた夫妻はまだ一度も大聖人にあったことがない門下だったようです。
本抄は当時着るものさえおぼつかない状態であった当時の大聖人に対して、
単衣(裏地のついていない一重の衣服)を送られた門下への感謝とその功徳
そしてこれまでの大難を通して、大聖人のみが仏の金言を実現したと
強く断言される内容となっています。
本抄の内容
本抄ではまず立宗してより二十数年間にひと時も休まることなく
難に遭ってきたことを回想され、後にも先にも法華経のためにこれほどの難に遭っているのは
大聖人ただお一人であるとご断言になられます。
そしてそのことは、完全に法華経の内容と一致しており、
もし大聖人が現れなかったならば、仏の言葉もすべて途絶えてしまっていたと
仰せになられます。
最後に、困窮を極める大聖人に対して単衣を送ったことは、
法華経の文字数であるvしたことになり、
そのことは、夫妻の祈りをかなえ、臨終のときは、すべてを守り、霊山にむかえてくださると仰せになられ
本抄を結ばれています。
拝読箇所の解説
日蓮、日本国に出現せずば、
如来の金言も虚しくなり、
多宝の証明(しょうみょう)もなにかせん。
十方の諸仏の御語(みこと)も妄語となりなん。
仏の滅後二千二百二十余年、
月氏・漢土・日本に「一切世間多怨難信
(一切世間に怨多くして信じ難し)」
の人なし。
如来の金言というのは、具体的には
法師品の「況んや滅度の後においてをや」と
安楽行品の「一切世間怨多くして信じ難し」です。
過去には天台大師なども法華経のために悪口を言われる難をうけたものの
最後には人々が天台大師の仏法を信受するにいたったので、
後半の「一切世間怨多くして信じ難し」に合致しないと仰せになられています。
すなわち、仏の滅後に、その予言通りに難に遭ったのは大聖人だけであると
仰せなのです。
多宝の証明というのは、通解に記載されている通り、
見宝塔品にて「法華経は真実である」と多宝如来が断言したことです。
日蓮なくば、仏語既に絶えなん。
法華経の予言通りに難に遭ったのは日蓮大聖人ただお一人であるので、
大聖人がもし誕生しせず、大難に合う人がいなければ
仏の言葉も全てなかったことになってしまっていただろうと仰せです。
深堀ポイント
これから御書を研鑽される方のために、深堀していきたいポイントを確認していきます。
大聖人のほどの難に遭わない私たちの信仰は中途半端なのか
今回の深堀ポイントは、
大聖人のほどの難に遭わない私たちの信仰は中途半端なのか、
その差をどう解釈すればよいのかという点です。
本抄で大聖人ご自身がご断言のように、
大聖人は法華経にとかれる大難を唯一実際に身に受けたただ一人の人物です。
その点においては、天台大師や伝教大師もおよばないとのご確信です。
しかも正法始まって以来の大難とは過酷を極めるものであり、
それは住居をおわれ、何度も襲撃、処刑の危機にさらされ、さらには二度の流罪にまで遭われています。
本抄をご執筆当時はすでにそれらの難の後ではあるものの、
身延に入山されてからの生活も、のんびりとした隠居生活とは程通い、
私たちの想像をはるかに超えるほど過酷なものでした。
そのことは本抄の後半部分に大聖人が記されています。
「簑を着て世を過ごしています。山林に入って果のない時は、
空腹のまま二、三日を過ごします。鹿の皮が破れれば、裸のまま三、四月を過ごしました。」
大聖人が極めて質素な生活をされていたことは私たちも知るところですが、
衣服さえも満足に切ることができず、2か月もの間、裸で過ごした時期があったとは衝撃的な事実です。
まさに生涯そのすべてが難とともにあったといっても過言ではない大聖人。
その一方で私たちの生活は、それとは比較するにも、おこがましいほどに恵まれた豊かな生活です。
もちろん現代でも困窮した状況にいる人は多くいます。
しかし法華経のために衣食住そのすべてがおぼつかないほどに追い込まれている人は皆無であると言えます。
私たちはこの差をどう考えるべきでしょうか。大聖人に比べて私たちには
大きな難が起きていないように感じます。
大聖人のみが唯一経文通りの難を受けた人であるならば、
私たちの法華経受持は中途半端であるということになるのでしょうか。
私たちと大聖人の難
このことを考察するヒントとしてまず考えたいのは、
大聖人の門下に対するご指導の中で、
自分と同様に衣食住が困るほどに正法弘教のために戦い抜きなさいと言われたことは
ただの一度もないということです。
大聖人が一貫して指導されていることとは、如説修行を実践していくということであり
すなわち
・末法における五種の妙行、すなわち御本尊を信じ南無妙法蓮華経を唱えていくこと
「苦をば苦とさとり、楽をば楽とひらき、苦楽ともに思い合わせて南無妙法蓮華経とうちとなえいさせ給え。」
衆生所遊楽御書
・法華経のすばらしさを語っていくこと
「力あらば、一文一句なりともかたらせ給うべし」
諸法実相抄
・邪智のものを折伏していくこと
「力あらん程は謗法をばせめさせ給うべし」
阿仏房尼御前御返事
この3点です。
そしてその法華経の行者に対して三類の強敵や三障四魔が起こってくるとの仰せなのです。
しかしその具体的な難のかたち、これは難であって、これは難ではないというような
「難のあるべき論」については一度も言及されたことはありません。
そしてもう一点考慮すべきは、時代背景です。
大聖人ご在世当時は執権政治であり、宗教正邪を理由に幕府にたてつくものは命を落とす時代です。
一方で現代においては、ある一定の民主的決定によって作られた法律のもと私たちは生活しており、信教の自由が保障された中にあって、少なくとも政府に物申したことだけで罰せられることはありません。
三類の強敵の出現や三障四魔が起きるとされる根源的な動機は
正法から人々を遠ざけることであり、
現代において考えれば、法華経の行者を生活的困窮に追い込むことは、
正法から人々を遠ざけるのに必ずしも効果的であるとは言えません。
少なくとも日本においては生活困窮者に対する最低限のセーフティネットがあり、
法華経の行者にとって、生活の困窮が信仰をやめる直接的な動機にはなりえない、むしろますます信心に励む人さえいるでしょう。
また本抄で大聖人ご自身が後にも先にもこのような大難に遭うのは自分のみであろうとご断言の箇所があり、
このことを逆に考えれば、難の大きさによってその人の成仏や信仰の正否は左右されないということになります。
それは大聖人の根本精神はどこまで行っても万人成仏にあるからです。
難の度合いが成仏に関連するのであれば、大聖人のこのご発言と精神は矛盾してしまうことになるからです。
如説修行抄には、
如説修行の法華経の行者には三類の強敵打ち定んで有る可し
(如説修行の法華経の行者には三類の強敵が必ず競い起こる)
や
兄弟抄には
行解既に勤めぬれば、三障四魔、紛然として競い起こる。
(仏法を持ち、行解(ぎょうげ)が進んできたときには、三障四魔が紛然として競い起こる)
と記されており、
また大聖人が
久遠実成の釈尊と皆成仏道の法華経と我等衆生との三つ全く差別無しと解りて妙法蓮華経と唱え奉る
と仰せの通り、
これらのご金言から、如説修行を行ったものは等しく難にあうと理解でき
そして大聖人と私たちではまったく差がないと言えます。
難の規模や激しさが違うように見えても
如説修行に取り組む者には同様に難が起きているということになります。
「紛然として」というのが非常に重要なポイントであり
多様な生き方が尊重されつつある現代にあっては、
障魔の働きも、より複雑に巧妙に分かりにくくなっていくのではないでしょうか。
ただ一つ共通して言えることは、
如説修行から人々を遠ざけようとするものはすべて障魔の働きであり
それはどんな些細な事であっても、一人の人を信仰から遠ざけるものは、
その見た目上の規模は全く関係がないということです。
極端に言えば、とてつもない病魔や経済苦がのしかかっても微動だにしない人にとって見れば、それはもはや難でもなく、
逆に、ある日疲れた心にふと浮かんだ「信仰をやめてもいいかもしれない」という小さなアイデアが一瞬で膨らみその人を信仰から遠ざける魔や大難につながることもあります。
あらゆる難に備えて、とにかく何があってもひたむきに信仰を貫いていこうと心に刻んでおくことが大切ではないでしょうか。
池田先生はつぎのようにいわれています。
「信心といっても、決して特別なことではありません。
まず、朝晩の勤行をしっかり励行し、自分の周りで悩みを抱えて苦しんでいる人がいたら、仏法を教えてあげればよいのです。
(中略)
そして、信心する人が出てきたら、互いに励まし合い、守り合っていくことです。」
新・人間革命 第三巻
日蓮大聖人は今から800年前、大慈悲をおこして
仏法消滅の危機に一人身を挺して難を受けられ、
私たちに妙法の光を届けてくださいました。
その戦いは私たちの想像を絶します。
しかしそのあまりにも尊い戦いに驚嘆するあまり、
自分たち自身の存在を過小評価するようなことがあってはいけません。
私たちには私たちにしかない戦いが今も必ずあるのです。
肝に銘じておきたいことは、「日蓮なくば、仏語既に絶えなん」とのご金言は、
生命の価値や可能性の大小を強調するものではないということです。
釈尊、大聖人、そして私たちを貫く生命の輝きは永遠に等しく輝いているものです。
あくまでも自分らしく、何があっても信仰を貫いていこうとするところに
その生命の光が輝き続けます。そしてその決意がまた、あなたの大切に思う人々の
幸福な人生へとつながっていくのです。
もっと教学にJOINして教学を楽しく深めよう!
サイトを見てみるもっと教学とは?
本サイトは創価学会での教学をより一層深めるためのサイトです。
人間革命や御書、その他教学に役立つ書籍のチェックリストや感想を投稿できます。
読了チェックシート
読了した本やチャプターを簡単に記録し、進捗を管理できます。
感想を投稿・シェア
読んだ御書や人間革命について感想を投稿できます。
題目カウント
毎日の唱題・勤行の記録ができます。ホーム画面で全国の合計題目数も見られます!
研鑽バッジ
研鑽の進捗や日々の研鑽状況に応じてバッジを付与します。
拍手機能
素晴らしいと思った活動に拍手をおくることができます。