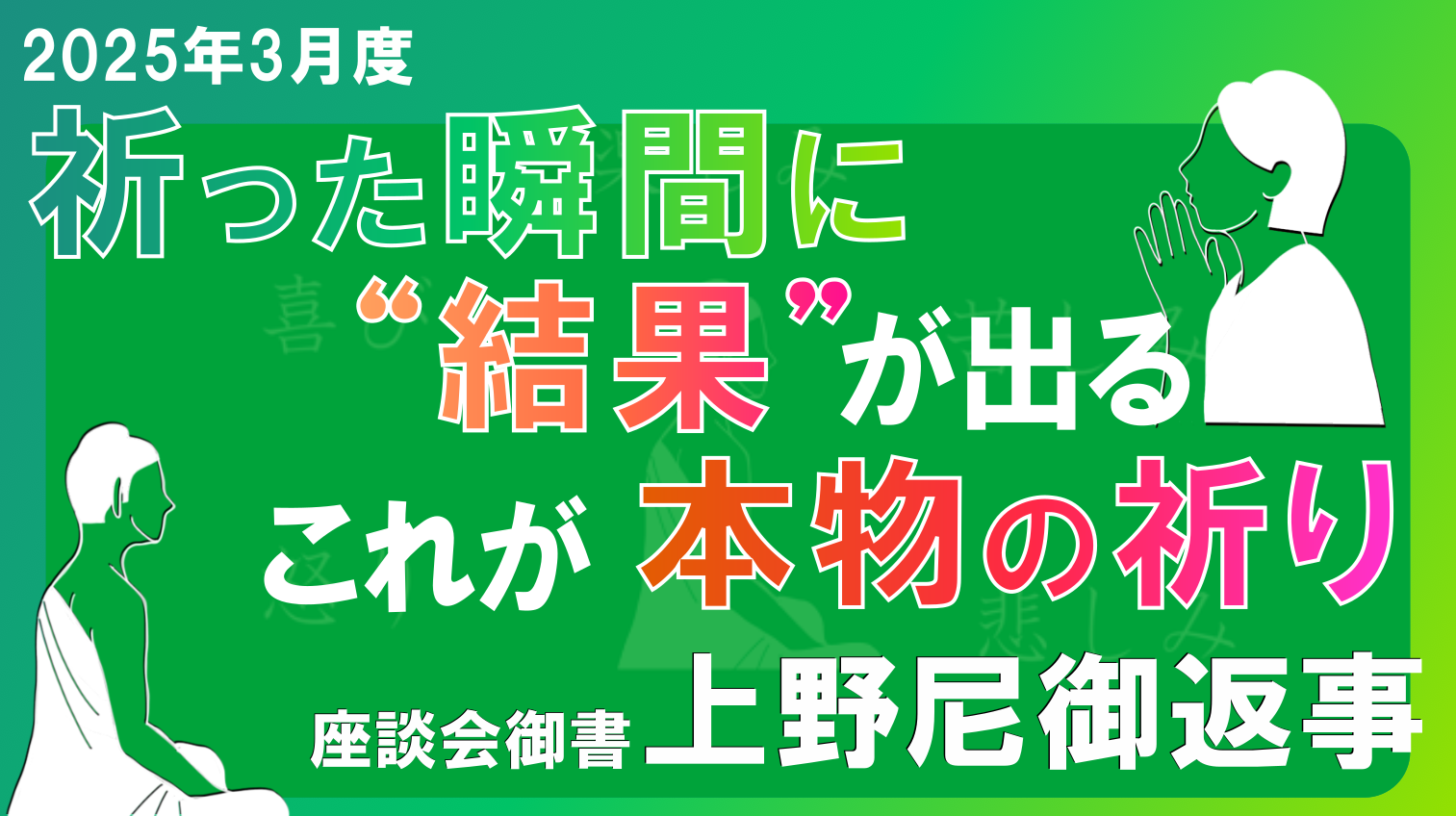
2025年3月座談会御書解説 上野尼御前御返事(烏竜遺竜の事)
YouTubeにアップしている御書解説の内容をこちらに書き起こしさせていただきます。文字で読みたい方はぜひご覧ください。
※動画編集作業の都合上、YouTube音声と以下の文章で多少表現が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
拝読御文
法華経と申すは、手に取れば
その手やがて仏に成り、
口に唱うればその口即ち仏なり。
譬えば、天月の東の山の端に出ずれば、
その時即ち水に影の浮かぶがごとく、
音とひびきとの同時なるがごとし。
故に、経に云わく
「もし法を聞くことあらば、
一りとして成仏せざることなけん」云々。
文の心は、この経を持つ人は、
百人は百人ながら、千人は千人ながら、
一人もかけず仏に成ると申す文なり。
全 1580ページ 6~9行目
新 1913ページ 3~7行目
通解
法華経というのは、手に取れば
その手が直ちに仏に成り、
口に唱えれば、その口がそのまま仏である。
譬えば、天の月が東の山の端に出れば、
その時、直ちに月の影が水に浮かぶように、
また、音と響きが同時であるようなものである。
ゆえに、法華経に「もし法を聞くことがあれば、
一人として成仏しない者はいない」と説かれている。
文の心は、この経を持つ人は、
百人は百人全て、千人は千人全て、
一人も欠けることなく仏に成るという文である。
背景と大意
本抄は弘安3年1280年11月15日、日蓮大聖人が59歳の時に身延であらわされ
駿河の国(現在の静岡県中央部)の門下である
南条時光の母、上野尼御前に贈られたお手紙です。
本抄は、尼御前のなくなった父の松野六郎左衛門入道の命日にあたり、
大聖人に供養したことに対する御返事となっています。
上野の尼御前は、夫の南条兵衛七郎とともに信心に励んだ門下です。
また後に最愛夫、兵衛七郎が若くして亡くなった後も純真な信心を貫き、
南条時光に代表されるように、後継の子どもたちを立派に育て上げた門下です。
まさに大聖人ご在世当時の一家で信仰を貫いた代表的な門下といえます。
本抄の内容
本抄の冒頭では、まず、蓮華が花と果実を同時につける植物であることを通して
法華経は、因果具時の法であり、
法華経を受持すれば直ちに仏になることを教えてくださっています。
つづいて、尼御前の父の追善回向に際して、
法華経以外を信仰する親類がいるために、
それが謗法になってしまうのではないかと不安を抱いていたことに対しての
回答が始まります。
大聖人は、これに対して、まず法華経こそが真実の法であり、
それは法華経において、多宝如来、そして十方の諸仏が証明しているところであると
ご断言になられます。
続いて、漢土の書家であった烏竜、そしてその子、遺竜についての故事をひいて
法華経による孝養こそが、最高の追善になることを教えてくださっています。
故事の内容はかいつまんで話すと次の通りです。
故事の内容
烏竜は仏法を嫌っており、そのことにより経文は書かないとの願いを立てているひとでした。
烏竜の死期が近づきその臨終のときには、その子遺竜にたいして
「どんなことがあっても法華経を書いてはならない」と遺言しました。
残された遺竜は、その遺言を固く守っていましたが、
ある時、司馬氏という法華経を信仰する大王が表れ
書家であった遺竜に法華経を書かせようとしました。
遺竜は父の遺言があるからと断ろうとしますが、
勅命であるから、その題目すなわち妙法蓮華経という文字だけでも書くように命じます。
遺竜は仕方なく、題目を書き、王に差し上げました。
遺竜は家に帰り遺言を破り法華経の題目を書いたことを激しく後悔し、
不孝の責めを免れることはできないと嘆き、それは食事ものどを通らないほどで
そのことにより、遺竜は死んだようになり、意識は朦朧としていました。
そんな時、ふと虚空を見ると、そこに天人が見え、話しかけてみると、
それはなくなった父であり、死後のことを語り始めます。
生前法華経を嫌ったことにより無間地獄におち、そのことによって地獄の苦しみを味わい
生前の行いを悔いていたが、息子である遺竜が法華経を書いたことによって
その苦しみから救われたというのです。
これが烏竜遺竜の故事のあらましです。
拝読箇所の解説
法華経と申すは、手に取れば
その手やがて仏に成り、
口に唱うればその口即ち仏なり。
譬えば、天月の東の山の端に出ずれば、
その時即ち水に影の浮かぶがごとし、
音とひびきとの同時なるがごとし。
この御文の直前には、法華経以外の一切の経について述べられています。
「一切経の功徳は先に善根を作して後に仏とは成ると説くかかる故に不定なり」
法華経以外の一切経が、成仏する前に善根を積む必要があり、
それがゆえに、成仏は不確かなものであると仰せです。
それに対して、法華経は因果具時の法であり、
受持すればただちに仏となると仰せです。
法華経の因果が常に同時であることを強調されます。
故に、経に云わく
「もし法を聞くことあらば、
一人として成仏せざることなかれ」と云々。
文の心は、この経を持つ人は、
百人は百人ながら、千人は千人ながら、
一人もかけず仏に成ると申す文なり。
だからこそ、法華経をもし聞くことがあったならば、
全ての人が一人残らず成仏していくことは間違いないのであると仰せになられています。
深堀ポイント
これから御書を研鑽される方のために、深堀していきたいポイントを確認していきます。
「なぜ仏界を瞬時に感じられる人が少ないのか」
今回の深堀ポイントは、
「なぜ仏界を瞬時に感じられる人が少ないのか」とはどういう意味なのかということです。
本抄において大聖人が最も強調されていることは、
法華経の因果倶時です。すなわち、原因と結果が同時であり、
それはすなわち法華経受持、即、成仏を示すものです。
さらに、本抄の中で大聖人が引用されている故事の中では、
子の遺竜が、王の命令に仕方なく従い法華経の題目を認めただけで
法華経誹謗の罪を犯した父烏竜が無間地獄から救われ成仏に導かれるということが書かれています。
法華経誹謗の罪は五逆罪よりも重く、それは顕謗法抄にある通りですが、
その罪をも妙法受持は消滅させたということになります。
しかし私たちの生活を振り返ってみれば、題目を唱えた瞬間に
自らの中にある仏の生命が直ちに輝きだし、日々の生活の困難や悩みが一瞬で消え楽しくなり一点の曇りもない澄み切った気持ちになるというようなことを経験した人が少ないのはなぜでしょうか。
むしろ祈っても祈ってもすぐには気持ちが変わらず、毎日何時間も題目を唱える、もしくは祈りの効果を直感的に感じられないがために、祈ること自体が苦手であるという人も多いかと思います。
大聖人仰せのことと実感が乖離
このことは本抄で大聖人が仰せのことと、まったく矛盾しているように感じられます。
大聖人はあくまで因果倶時と仰せなのであり、徐々に仏界が開くということや、祈ってもその効果を感じられない人がいるなどとは一言も仰せではないからです。
それではこの法門と私たちの実感の乖離の原因はどこにあるのでしょうか。
大聖人は末法のご本仏であり、そのお言葉は言わずもがなすべて真実であり、受持即観心は絶対です。
だとすれば仏界は確実に湧現しているはずだけれども、それを本人が実感できないのはなぜか
その最大の理由と考えられるのは、私たちの成仏観のズレです。
誤った成仏観
仏界を何か特別な心理状態、無敵の状態のようにとらえているひとは多くいるかと思います。
何があっても楽しい、気持ちいい、苦しみ悩み事が一気にスカッと消え去り幸福を感じること、
その境涯を期待して祈っているという人は多いのではないでしょうか。
しかし池田先生は次のようにおっしゃられています。
「寿量品の「久遠の仏」とは
一切衆生のことなのです。
私どものことです。
凡夫は凡夫のままで仏なのです。
命に差別はない。
平等です。
平等に仏です。
違うのは、
それを自覚しているか否か、
その「心」の違いだけです。」
「法華経の智慧」如来寿量品(第十六章)永遠の生命とは〈下〉
本来、喜び、怒り、悲しみ、苦しみ、楽しみ、それらのあらゆる感情を備えていてこそ仏なのであり、
そしてそれはまさに私たちの姿そのものです。苦しみでさえも「楽しんでいく」ことと、
苦しみを感じなくなり「楽しくなる」ということは似て非なるものであり、
絶対的幸福境涯とは明らかに前者の事をさしています。
後者の、苦しみを感じず楽しくなることには必ず無理や限界があり、
また凡夫の心の動きとして歪なものに感じられます。
大聖人は次のように仰せです。
「苦をば苦とさとり、楽をば楽とひらき、
苦楽ともに思い合わせて南無妙法蓮華経とうちとなえいさせ給え。これあに自受法楽にあらずや。」
衆生所有楽御書
苦しいことを楽しく感じられるようになることも一つの境涯革命の形かもしれません。
しかし仏界の本質とは、そこに苦しみがあり、そしてその苦しみを身心の痛みとして素直に認識しつつも、
しかしそれでも南無妙法蓮華経を唱えていくところに、
自受法楽すなわち、仏の境涯があるということです。
どんなことも楽しく感じられるようになるのが仏の本質ではなく、
どんな時でも、南無妙法蓮華経を唱え抜いていく姿こそが仏の本質だということです。
祈っていても、苦しい時は苦しい。しかしそれでも考え、智慧を働かせ、何とか状況を打開しようと行動する
現実を見れば、時には失敗を重ね、何らかの挑戦を諦め、考え抜いた末に撤退せざるを得ない場合もあるでしょう。
しかしそれこそが現実で生きる真実の仏の姿なのです。
現実を踏まえずこの世界の原理原則を度外視して、やみくもに走り続けることが信仰の力ではありません。
それはまさに超常現象的、神頼み的信仰であり、現実を遊離した念仏的信仰と言えるかもしれません。
仏法は道理であり、この世界の理と矛盾しません。超常現象を起こすものではないのです。
私たちは何を目指しているのか
それでは私たちの目指す先とはどこにあるのでしょうか。
仏の姿をもってしても現実の上での成功や幸福を約束されないのであれば、
そもそも成仏する意味などあるのかと疑問を抱く人も多いかと思います。
逆に言えば私たちが南無妙法蓮華経と唱える時、そこで私たちに湧現している仏の境涯の実態とは
何なのでしょうか。
この問いに関しては、一つのこれという答えはなく人によって感じるものは違うかもしれません。
また同じ人であっても、時と場合により信仰の意味が違うということがあると思います。
しかしあえてこの信仰の力、仏界とは普遍的にどのようなことをいうのかと問われれば、
それは、希望を失わない人になる、ということではないでしょうか。
希望を失わない人は、生きていくエネルギーを失いません。
それは、人生の失敗、挫折、決して順風満帆ではない時においてもです。
たとえ八方手を尽くしきり、それでもうまくゆかず、どうしようもないと思える時でさえも、
ひとたび南無妙法蓮華経を唱えるならば、何もないはずの暗闇にただちに希望の光を灯すことができます。
その希望の光とは、どこか遠くに一筋の光が見えるというものではなく
自身の内に灯る光です。
何一つとして手掛かりがない中、それでも、どうにか前を向こうとする究極の姿と言えます。
池田先生は希望について次のようにおっしゃられています。
「希望ほど強いものはない。妙法は「永遠の希望」である。何があっても希望を失わない人こそが幸福者である。」
大聖人が仰せのように、法華経を受持するとき、すなわち
南無妙法蓮華経を唱える時、そこに仏界が湧現していることは間違いありません。
しかしその仏界とは、摩訶不思議な力や誰もが驚く前代未聞の強靭なメンタルを突如として備えさせるものではありません。
エキセントリックで派手な奇策を思いつき遂行させるものでもありません。
失敗をせず成功ばかりを手にできるようになることでもありません。
苦しみを消し楽しい感情ばかりにすることでもありません。
あなたが、あなたらしいあらゆる境涯を備えた一人の凡夫として、
今目の前にある自他の悩み、苦しみ、課題に対して、
ひたむきに最善を尽くし続けていこうとするその姿に仏界が湧現しているのです。
そしてその先に、苦しみの渦中では想像だにしなかった大歓喜感涙の情景を目にするのです。
もっと教学にJOINして教学を楽しく深めよう!
サイトを見てみるもっと教学とは?
本サイトは創価学会での教学をより一層深めるためのサイトです。
人間革命や御書、その他教学に役立つ書籍のチェックリストや感想を投稿できます。
読了チェックシート
読了した本やチャプターを簡単に記録し、進捗を管理できます。
感想を投稿・シェア
読んだ御書や人間革命について感想を投稿できます。
題目カウント
毎日の唱題・勤行の記録ができます。ホーム画面で全国の合計題目数も見られます!
研鑽バッジ
研鑽の進捗や日々の研鑽状況に応じてバッジを付与します。
拍手機能
素晴らしいと思った活動に拍手をおくることができます。