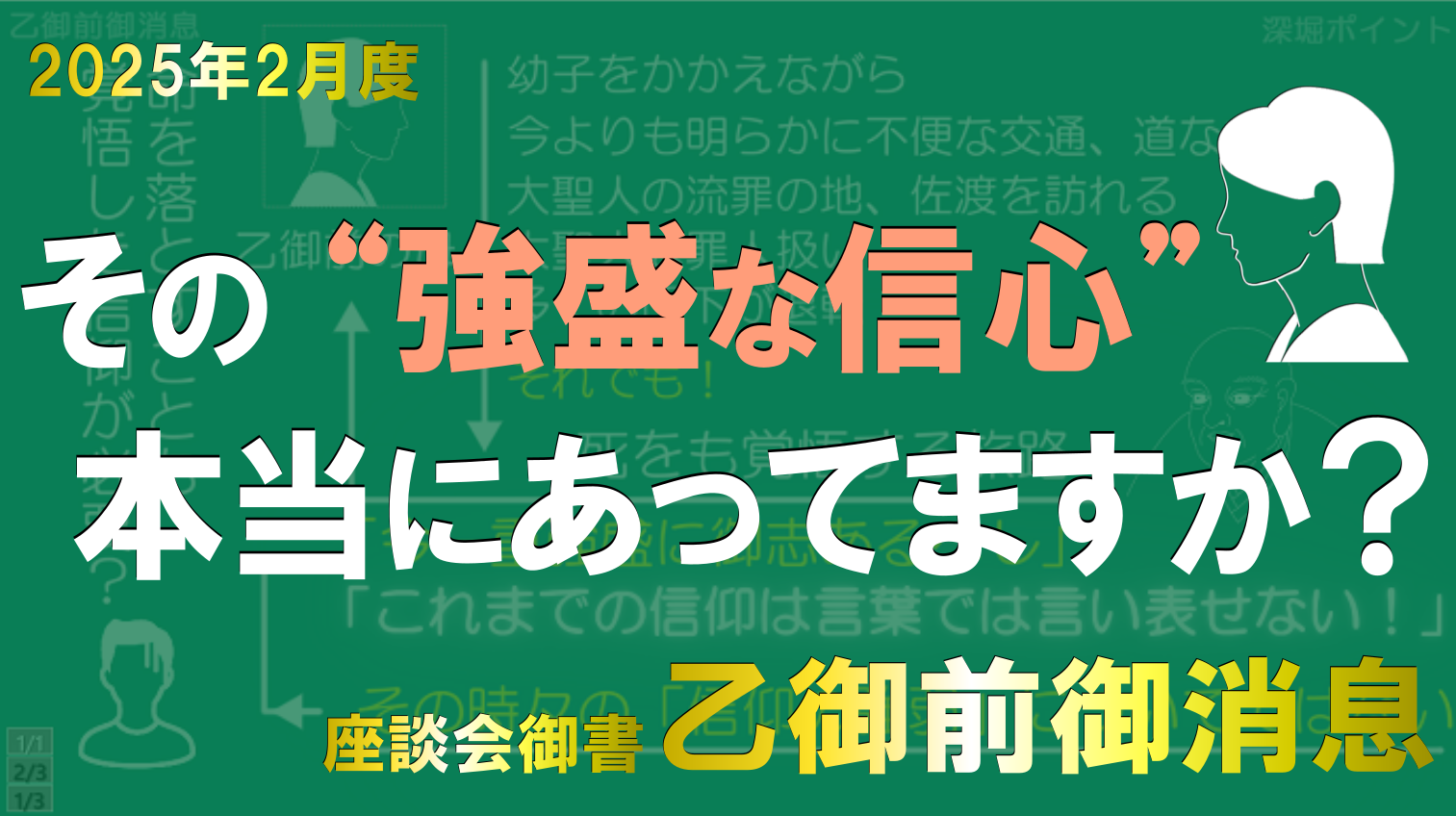
2025年2月座談会御書解説 乙御前御消息
YouTubeにアップしている御書解説の内容をこちらに書き起こしさせていただきます。文字で読みたい方はぜひご覧ください。
※動画編集作業の都合上、YouTube音声と以下の文章で多少表現が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
拝読御文
されば、妙楽大師のたまわく
「必ず心の固きに仮って、神の守り則ち強し」等云々。
人の心かたければ、神のまぼり必ずつよしとこそ候え。
これは御ために申すぞ。
古の御心ざし申すばかりなし。
それよりも今一重強盛に御志あるべし。
その時はいよいよ十羅刹女の御まぼりも
つよかるべしとおぼすべし。
御書全 1220ページ 9~12行目
新 1689ページ 13~16行目
通解
(法華経を信ずる者は諸天善神に守られる)
それゆえ、妙楽大師は
「心が堅固であれば、必ず神の守りも強いのである」と言われている。
その人の信心が固ければ、諸天善神の守りは必ず強い、ということです。
これは、あなたのために申し上げるのである。
これまでの、あなたの信心の深さは、言い表すことができない。
しかし、それよりもなお一層の強盛な信心に励んでいきなさい。
その時は、ますます十羅刹女の守護も強くなると思いなさい。
背景と大意
本抄は建治元年1275年8月4日日蓮大聖人が54歳の時に身延であらわされ
鎌倉に住む門下であった乙御前とその母日妙聖人に与えられたお手紙です。
題号は「乙御前御消息」となっていますが、その内容から
実質的にはその母である日妙聖人に与えられたお手紙とされています。
お手紙の内容から、乙御前はまだ幼子であったという点と、
「夫と別れている」ことに言及されていることからもそのことがわかります。
本抄のなかでは「日妙聖人」という名前は出てきませんが、
別のお手紙「日妙聖人御書」において、その不惜身命の信仰をたたえられ
大聖人自らが、乙御前の母に対して「日妙聖人」という名前を送られています。
大聖人が門下に対してお名前を送られる例はいくつかありますが、
「聖人」との名前を送られたことは数少なく
そこには人としてほかの模範となる人物、修行を積んだ偉大な信仰者という意味が込められています。
乙御前の母は、鎌倉時代とくに、飢饉や疫病で多くの人が苦しむ時代に、
夫とも別れ、更には幼子を抱えるという非常に大変な状況の中で、
遠路はるばる佐渡流罪中の大聖人、そして本抄においては身延まで足を運んで
大聖人のもとを訪れた門下です。
しかも佐渡を訪れた際には、十分な蓄えがあるわけではなく、帰りの宿代もおぼつかず、
そのことを知った大聖人が自ら宿主に借金をして工面したと言われています。
乙御前の母に贈られたいくつかのお手紙、いずれにおいても
そのけなげな信心がいかに稀有なものであるか、その信心を最大限にほめたたえられています。
本抄の内容
本抄はまず、法華経こそが悪人や女人など
法華経以前には成仏できないとされた人を含めた万人の成仏を
約束する唯一無二の法であり、他の経典との勝劣、浅深は明らかであると仰せです。
つづいて蒙古襲来当時の政府の哀れな狼狽ぶりを指摘し、
その原因はあやまった真言の思想を取り入れ
法華経の行者を虐げたゆえであると喝破されます。
そして、そのような乱世の時代にあって、夫もおらず
一人で幼子を育てながら信仰に励む乙御前の母は優れた女性であるとご称賛されます。
また、その信仰が強ければ、より一層の諸天の加護は、過去の仏典、
また大聖人ご本人のご経験から間違いないと仰せになられます。
今後国がますます悲惨な状況になり、生活の先行きは不安ではあるが
何かあればいつもで身延においでなさいとの甚深のお言葉をかけられます
最後に、娘の乙御前の成長に期待を寄せられ、本抄を結ばれています。
拝読箇所の解説
されば、妙楽大師のたまわく
「必ず心の固きに仮って、神の守り則ち強し」等云々。
人の心かたければ、神のまぼり必ずつよしとこそ候え。
妙楽大師とは、中国にいた僧であり、
天台大師の法華経の解釈を支持し、天台の教学を整備した人物です。
その人物がと断言していると仰せの箇所です。
また妙楽大師がそのように断言するのは
法華経薬王品など、法華経の各所に、諸天善神は法華経の行者を護ることになっているとの
約束が記されているからにほかなりません。
これは御ために申すぞ。
古の御心ざし申すばかりなし。
それよりも今一重強盛に御志あるべし。
その時はいよいよ十羅刹女の御まぼりも
つよかるべしとおぼすべし。
背景と大意でも申し上げた通り、
乙御前の母の信仰は、大聖人が日妙聖人とお名づけになるほどに
けなげで賞賛すべき者であり、これまでの信仰については
何も言うべきことがないと仰せです。
しかしそれでも、いよいよの信心を起こしていくべきであると仰せです。
そうしてより一層の信心に励んでいくとき、
十羅刹女、つまりは諸天の加護も一層強くなっていくと
激励されているのです。
深堀ポイント
これから御書を研鑽される方のために、深堀していきたいポイントを確認していきます。
よく見る「強盛の信心」とはどんな意味か分からない
今回の深堀ポイントは、
「強盛の御志」とはどういう意味なのかということです。
今回の大白蓮華においては、
「強盛に御志あるべし」の箇所は、
「強盛な信心に励んでいきなさい」との通解があてられてます。
大聖人の様々な御書においても、
この「強盛な信心」という言葉はたびたび見られ、
たとえば有名なところでいえば、衆生所遊楽御書においては
四条金吾に対して
いよいよ強盛の信力をいたし給え。と仰せになられています。
歴代会長のご指導においても同様です。
第二代会長戸田先生は、
「強盛に信心するならば、経文において明らかなごとく、新しく強き生命力を得て、事業に、健康に、生き生きとした生活が始まってくる」
第三代会長池田先生は
「強盛な信心を奮い起こして広宣流布に生き抜いていくならば、病をはじめ、どんな災いもすべて転換し、必ず幸福への飛躍台にしていくことができるのだ。」
このようにご指導の中にたびたび登場する、ある意味で聞きなれた言葉ですが、
よくよく考えてみると「強盛な信心」とはどんな信心のことなのか説明できる人は少ないのではないでしょうか。
「強盛」の辞書的な意味を調べると
勢いが強くて盛んなこと。また、そのさま。とあります。
その言葉からは激しさや力強さをイメージする人が多いと思います。
「いよいよ強盛の」と聞くと、終わらない激しい戦いを想像し、
気重になってしまう人も多くいるはずです。
しかし力強い信仰とはいったいどんな信仰でしょうか。
題目を数多く唱えることでしょうか
弘教を数多く成し遂げることでしょうか
メンタルに強い負担がかかる行動でしょうか。
それも一つの答えなのかもしれません。
しかし、「数多く」ということになると、それは常に相対的なものとなり
力強い信仰とは何かということに対して、決定的な答えにはなりえないように思えます。
精神的な負荷が大きいということも同様です。
「強盛の信心」の本来の意味
乙御前の母は、幼子をかかえながら、今よりも明らかに不便な交通、道なき道をいき、大聖人の流罪の地、佐渡を訪れています。
しかも、一般的に言えば当時の大聖人は罪人です。
多くの門下が難を恐れ退転してしまう中、それでも信仰を貫き、大聖人のもとを訪れる道中も、
まさに死をも覚悟した道であったと想像されます。
それは本抄に記されている通りです。
大聖人は、そのだれよりも強い信仰心をもったその門下に対して
「今一重強盛に御志あるべし」と仰せなのです。
これだけを見れば、諸天の加護を得るためには、
命を落とすことも覚悟した、「強い信心」が必要なのかと何となく途方に暮れてしまう気もします。
しかし見逃してはならないのは、
大聖人はこれまでの乙御前の母の信仰についても
「これまでの、あなたの信心の深さは、言い表すことができない。」と最大限のご賞賛を送られていることです。
つまり「今一重の強盛さ」というものは、その時々の信仰心とそれに伴う行動をより一層強めよという意味ではないのではないか
ということが想像されてきます。
大聖人は本抄のなかで、乙御前の母に対して
再度、「強盛の信心を」と語りかけられる箇所があります。
いよいよ強盛の御志あるべし、(中略)青き事は藍より出でたれども・かさぬれば藍よりも色まさる、同じ法華経にては・をはすれども志をかさぬれば・他人よりも色まさり利生もあるべきなり
この青と藍の関係の中で、強盛を示すために用いられているのは、「重ねる」という表現です。
つまり本抄において、「強盛の信心」が指し示すものとは、その時々の信仰の強度とそれを反映する誰もが驚くような決意や行動などというよりも、むしろ弛みなく塗り重ねられ、そのたびに色の濃さをましていくような信仰のことです。
「強盛」とはたゆみなく塗り重ねること
新人間革命でも次のようなシーンがあります。
「火の信心」とは一時的には燃え上がっても、すぐに消えてしまう信心であり、
水が流れるように持続していく「水の信心」こそが、強盛な信心の姿であると教わってきた。(中略)
『水の信心』を貫いていくならば、必ず幸せになれますよ
新人間革命 第一巻「新世界」
そしてまた、水の信心はということについてはつぎのように語られています。
『水の信心』は、派手で目立った行動はなくとも、心堅固に、常に水が流れるように、不撓の決意と使命感をもって、
生涯、信・行・学を持続し抜いていく人の信心です。
新人間革命 第二十六巻「法旗」
つまり信心強盛とは、少しずつでも弛みなく前進し続けること、
南無妙法蓮華経の祈り、
そして自他共にその仏性を開いていく振る舞い、
その祈りと行動を強め、意義を深める教学
一歩ずつ確かな足跡を残していくことこそが強盛な信心の意味するところなのです。
「強盛」とは時代をこえても流れ続ける生活の骨髄
またこれは私の個人的な感想ですが、
本抄においては、
信心強盛の表現として
従藍而青の比喩が用いられている点、
またそもそもの題号が「乙御前御消息」と日妙聖人の幼い娘宛なっている点からして、
「強盛な信心」の意味するところが、個人のおける水の信心を強調されることだけにとどまらず、
次世代へと途切れることなく信仰を継承していくことの重要性を訴えておられるように感じられてなりません。
そしてそれは必ずと言っていいほど、燃え上がるような火の信心、短兵急な信仰ではなしえないことだと言えます。
付け焼刃で、呪いを信じるかのようなあいまいな神秘主義の信仰ではなく
生命の骨髄となる着実な信仰です。
池田先生は次のように教えてくださっています。
“いよいよ強盛の信心”と言っても、それは何か特別なものではありません。
きっと、誰もが「ここまで頑張ってきたのになぜ?」「自分の祈りはかなわないのでは」と、歩みを止めてしまいそうになることがあるでしょう。その時こそ、「いよいよ」自身の信心が試されているのだと、心を決め、より深き信心で立ち上がることが大事です。
何があっても、御本尊を疑わず、絶対勝利の信心を確信し、「昨日より今日」「今日より明日」と、自分らしく一歩ずつ前へ進んでいくこと。これが“いよいよ強盛の信心”です。その心で積み上げる日々の挑戦が、何ものにも負けない自身を築き上げていくのです。
〈華陽*GOSHO TIME〉 ~池田華陽会 御書30編を学ぶ~
信心は生活の上にしか体現できません。
それは信心即生活ということです。
生活の中にある、あらゆる挑戦の中にこそ信心を体現する場所があり、
その中でこそ強盛の信心を示していけるのです。
あなたの今一重の御志こそが、あなたのともに生きてゆく人々のより豊な人生の源泉になってゆくのです。
もっと教学にJOINして教学を楽しく深めよう!
サイトを見てみるもっと教学とは?
本サイトは創価学会での教学をより一層深めるためのサイトです。
人間革命や御書、その他教学に役立つ書籍のチェックリストや感想を投稿できます。
読了チェックシート
読了した本やチャプターを簡単に記録し、進捗を管理できます。
感想を投稿・シェア
読んだ御書や人間革命について感想を投稿できます。
題目カウント
毎日の唱題・勤行の記録ができます。ホーム画面で全国の合計題目数も見られます!
研鑽バッジ
研鑽の進捗や日々の研鑽状況に応じてバッジを付与します。
拍手機能
素晴らしいと思った活動に拍手をおくることができます。